
- カラシとマスタードの最大の違いは「原料の種」と「酢の有無」です。
- カラシの辛さは鼻にツーンと抜け、マスタードはマイルドな酸味が特徴。
- 和がらしはカラシの一種で、洋がらしはマスタードの別名なんです。
- 料理によって使い分けることで、それぞれの持ち味を最大限に活かせます。
- 粉からしを練るときは、熱湯ではなく「ぬるま湯」を使うのが鉄則でした。
おでんにはカラシ、ホットドッグにはマスタード。何気なく使うけど違いは何でしょう?
元料理人の私が原料から味、料理がもっと美味しくなる使い分けまで解説します。
カラシとマスタードの決定的な違い
「カラシ」と「マスタード」、この二つの最も大きな違いは次の2点です。
- 使われる種の種類
- 酢を加えるかどうか
日本のカラシは、鼻にツーンと突き抜ける強い辛さが特徴です。
一方、海外から来たマスタードは、お酢が入っているため、酸味があってマイルドな辛さになります。
| 項目 | カラシ(和がらし) | マスタード(洋がらし) |
|---|---|---|
| 主な原料 | オリエンタルマスタードシード | イエローマスタードシードなど |
| 辛さの特徴 | 鼻にツーンと抜ける強い辛さ | マイルドな辛さと酸味 |
| 主な加工 | 水やぬるま湯で練る | 酢、砂糖、香辛料などを加える |
| 色 | 濃い黄色 | 鮮やかな黄色 |
| 相性の良い料理 | おでん、豚まん、シュウマイ | ホットドッグ、サンドイッチ |
プロの失敗談:粉からしの練り方
私が駆け出しの料理人だった頃、急いで粉からしに熱々のお湯を注いでしまったことがあります。
結果、全く辛くない黄色いペーストに…。
実はカラシの辛味成分は熱に非常に弱く、40℃程度のぬるま湯で練るのが鉄則。
この失敗のおかげで、素材の特性を理解する重要性を学びました。
カラシとマスタードの歴史
マスタードの起源は古代エジプト
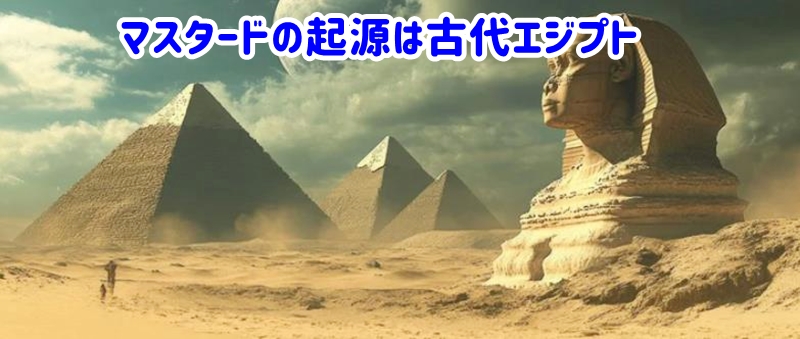
マスタードの歴史は紀元前3000年頃の古代エジプトまで遡ります。
古代ローマでは、マスタードシードをワインやお酢と混ぜて肉料理の付け合わせとして楽しんでいました。
中世ヨーロッパでは、フランスのディジョン地方でマスタード作りが盛んになり、
「ディジョンマスタード」として世界的に有名になりました。
日本のカラシの歴史
日本にカラシが伝わったのは奈良時代と言われています。

正倉院の文書にも「芥子(からし)」の記録が残されています。
江戸時代になると庶民の食卓にも広く普及し、蕎麦やおでんなどの和食に欠かせない調味料となりました。
マスタードシードとは?3種類の種を徹底解説
カラシやマスタードの原料となる「マスタードシード」には、主に3つの種類があります。
1. オリエンタルマスタードシード(ブラウンマスタード)
- 日本の和がらしの主原料
- 非常に強い辛味を持つ
- 鼻にツーンと抜ける刺激的な辛さ
- 主な使用例: 和がらし、おでん用のカラシ
2. イエローマスタードシード(ホワイトマスタード)
- 欧米のマスタードの主原料
- マイルドな辛さ
- 鮮やかな黄色
- 主な使用例: イエローマスタード、ホットドッグ用マスタード
3. ブラックマスタードシード
- 中間的な辛さ
- 香ばしい風味とプチプチとした食感
- 主な使用例: 粒マスタード、インドカレーのスパイス
| 種類 | 辛さレベル | 色 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| オリエンタルマスタード | ★★★★★ | 褐色 | 和がらし |
| イエローマスタード | ★★☆☆☆ | 黄色 | アメリカンマスタード |
| ブラックマスタード | ★★★☆☆ | 黒褐色 | 粒マスタード |
参考文献:マスタードシードの種類については、エスビー食品株式会社で詳しく解説されています。
なぜ味が違うの?辛味成分の科学的メカニズム

カラシの辛味成分「シニグリン」
和がらしのオリエンタルマスタードシードには、「シニグリン」という配糖体が含まれています。
この物質は水分と混ざると、「ミロシナーゼ」という酵素が働き、辛味成分である「アリル芥子油(アリルイソチオシアネート)」が生成されます。
化学反応:
シニグリン + 水 + ミロシナーゼ → アリル芥子油(辛味成分)
なぜ熱湯で練ると辛くならないのか?
ミロシナーゼという酵素は熱に弱く、60℃以上の熱湯を使うと失活してしまい、辛味成分が生成されなくなります。
そのため、40℃程度のぬるま湯で練るのがベストです。
マスタードの辛味がマイルドな理由
マスタードを作る際に加える「酢」が、辛味成分の生成を抑制します。
酢の酸性環境下では、ミロシナーゼの働きが弱まるため、辛味がマイルドになるのです。
なぜからしはチューブで、マスタードは瓶なのか?
からしがチューブ入りの理由
- 鮮度管理 – 辛味成分が揮発しやすく、チューブなら空気に触れる時間を最小限にできる
- 使用量の少なさ – 辛味が強いため少量ずつ使いやすい
- 携帯性 – 外食先でも使える
マスタードが瓶入りの理由
- 保存性の高さ – 酢が含まれているため長期保存が可能
- 使用量の多さ – マイルドな辛さでたっぷり使うため瓶が便利
- 粒マスタード – チューブから出しにくい
実は、からしのチューブ入りは日本独自の文化です。
参考文献:
からしのチューブ容器については、日本からし協同組合の公式サイトで詳しく解説されています。
マスタードの種類を完全網羅

1. イエローマスタード(アメリカンマスタード)
鮮やかな黄色でマイルドな辛さ。ホットドッグ、ハンバーガーに最適。最もポピュラーなマスタードです。
2. ディジョンマスタード
フランス・ディジョン地方発祥。白ワインやワインビネガーを使用し、上品で深みのある辛さが特徴。鶏肉のソテーやステーキソースに最適。
3. 粒マスタード(ホールグレインマスタード)
マスタードシードを粗挽きまたは粒のまま使用。プチプチとした食感が楽しめます。ソーセージ、ローストビーフと相性抜群。
4. イングリッシュマスタード
イギリス伝統のマスタードで、強い辛さが特徴。ローストビーフの定番です。
5. ハニーマスタード
はちみつを加えた甘いマスタード。甘みと辛みの絶妙なバランスで、チキンナゲットやサラダドレッシングに人気。
6. ビールマスタード
ビールを加えて作られ、独特の苦味とコク。ソーセージやプレッツェルに合います。
参考文献:
マスタードの種類については、キユーピー株式会社の公式サイトで詳しく紹介されています。
料理のプロが教える!効果的な使い方

カラシが活きる料理
ツーンとした辛さが料理の味を引き締め、脂っこさをリセット。
- おでん – 大根や練り物に刺激的なアクセント
- 豚まん・シュウマイ – 肉の脂っぽさを和らげる
- とんかつ – ソースに混ぜて味を引き締める
- 納豆 – 風味が引き立つ
マスタードが活きる料理
酸味とマイルドな辛さが素材の味を引き立て、コクと深みを与えます。
- ホットドッグ・ソーセージ – 王道の組み合わせ
- サンドイッチ – ハムやチーズと相性抜群
- ステーキ・鶏肉のソテー – 本格的なソースに
- ポテトサラダ – マヨネーズに混ぜて風味アップ
おすすめレシピ
からしを使った絶品レシピ
きゅうりの和がらし漬け

材料(4人分):
- きゅうり:3本
- 練り和がらし:大さじ1
- 砂糖:大さじ2、酢:大さじ2、塩:小さじ1/2
作り方: きゅうりを乱切りにして塩もみし10分置く。水気を絞り、和がらし・砂糖・酢を混ぜて和え、冷蔵庫で30分以上冷やす。
豚肉の和がらし焼き

材料(2人分):
- 豚ロース肉:200g
- 練り和がらし:小さじ1
- 醤油・みりん・酒:各大さじ1
作り方: 調味料を混ぜて豚肉を10分漬け込み、フライパンで両面をこんがり焼く。
マスタードを使った本格レシピ
鮭のディジョンマスタード焼き
材料(2人分):
- 鮭の切り身:2切れ
- ディジョンマスタード:大さじ2
- マヨネーズ:大さじ1、レモン汁:小さじ1
- パン粉:大さじ2
作り方: 鮭に塩・こしょうをふり、マスタード・マヨネーズ・レモン汁を混ぜて塗る。パン粉をまぶし、200℃のオーブンで15〜20分焼く。
ハニーマスタードチキン
材料(2人分):
- 鶏もも肉:2枚
- ハニーマスタード:大さじ3
- 醤油:大さじ1、にんにく:1片
作り方: 鶏肉を一口大に切り、調味料で30分漬け込む。フライパンで皮目から焼き、両面こんがり焼いてタレを絡める。
カラシとマスタードは代用できる?
カラシでマスタードを作る方法
- 練り和がらし:大さじ1
- マヨネーズ:大さじ3
- 酢:小さじ1、砂糖:小さじ1/2
混ぜ合わせるだけでマスタード風の調味料が完成。
アレンジ:
- ハニーマスタード風 → はちみつ小さじ1を追加
マスタードでカラシを再現
- イエローマスタード:大さじ2
- わさび:小さじ1/2
- 醤油:小さじ1/2
わさびを加えることで、ツーンとした刺激が加わります。
代用可否の判断基準
| 料理 | カラシ→マスタード代用 | マスタード→カラシ代用 |
|---|---|---|
| おでん | △(風味が変わる) | × |
| ホットドッグ | ○(可能) | △ |
| サンドイッチ | ○ | △ |
からしとマスタードの健康効果・効能
カラシの健康効果
- 食欲増進効果 – 消化液の分泌を促進
- 消化促進作用 – 胃腸の働きを活発に
- 血行促進 – 体を温める効果
- 抗菌・防腐作用 – 食品の保存性を高める
- 抗酸化作用 – 活性酸素を除去
マスタードの健康効果
- 消化促進 – 特にタンパク質の消化を助ける
- 代謝アップ – 体の代謝を上げる
- 酢の健康効果 – 血糖値上昇を緩やか、疲労回復
注意点
- 胃腸が弱い方は食べ過ぎに注意
- 妊娠中・授乳中は大量摂取を避ける
- マスタードアレルギーの可能性もあり
正しい保存方法
チューブ入りカラシ
- 開封前: 常温の冷暗所
- 開封後: 必ず冷蔵庫で保存、キャップをしっかり閉める
- 使用期限: 開封後1〜2ヶ月
粉カラシ
- 密閉容器に入れ替えて冷蔵庫保存
- 開封後は3〜6ヶ月以内に使い切る
- 練った後はその日のうちに使い切る
瓶入りマスタード
- 開封前: 常温保存可能
- 開封後: 冷蔵庫で保存、清潔なスプーンを使用
- 使用期限: 開封後2〜3ヶ月
風味が落ちたサイン
カラシ: 辛味がない、茶色に変色、水分分離、異臭
マスタード: 極端に酸味が強い、色が暗い、カビ、油が分離
よくある質問(Q&A)
Q. 和がらしと洋がらしの違いって何?
A. 呼び方の違いです。「和がらし=カラシ」「洋がらし=マスタード」と覚えましょう。
Q. 練りからしが辛すぎる時は?
A. 少量のお酢やマヨネーズを混ぜると辛さがマイルドになります。
Q. マスタードシードから自分で作れる?
A. はい、作れます。
基本レシピ:
- マスタードシード(粉末):50g
- 水:大さじ2、白ワインビネガー:大さじ2
- 塩:小さじ1/2、砂糖:小さじ1
混ぜ合わせて一晩寝かせると完成。
参考文献:
自家製マスタードの作り方は、辻調理師専門学校で詳しく紹介されています。
Q. ペットに食べさせても大丈夫?
A. 絶対にダメです。犬や猫にとって有害な食品です。
Q. 賞味期限切れは食べられる?
A. カビ、変色、異臭がなければ自己責任で可能ですが、風味は落ちています。
できるだけ期限内に使い切りましょう。
Q. カラシやマスタードでダイエットできる?
A. 代謝を上げる効果はありますが、単体でダイエット効果を期待するのは現実的ではありません。
バランスの良い食事と運動と組み合わせましょう。
Q. 子供に食べさせても大丈夫?
A. 一般的には3歳以降が目安。最初は極少量から試し、マイルドなマスタードから始めるのがおすすめです。
まとめ
- カラシとマスタードの違いは、原料の種と酢の有無
- カラシはオリエンタルマスタードシード、マスタードはイエローマスタードシードが主原料
- カラシは鼻に抜ける強い辛さ、マスタードは酸味のあるマイルドな辛さ
- 辛味成分はシニグリンから生まれるアリル芥子油
- マスタードシードには3種類があり、それぞれ辛さが異なる
- 粉からしは40℃のぬるま湯で練る
- からしがチューブでマスタードが瓶なのは鮮度管理と使用量の違い
- 健康効果:消化促進、血行促進、抗菌作用など
- 開封後は必ず冷蔵庫で保存
- 料理によって使い分けることで、味わいが格段にアップ
普段何気なく使っている調味料にも、深い世界があります。
次におでんやホットドッグを食べる時、ぜひこの記事を思い出してください。
調味料選びは、料理の味を左右する重要な要素です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント