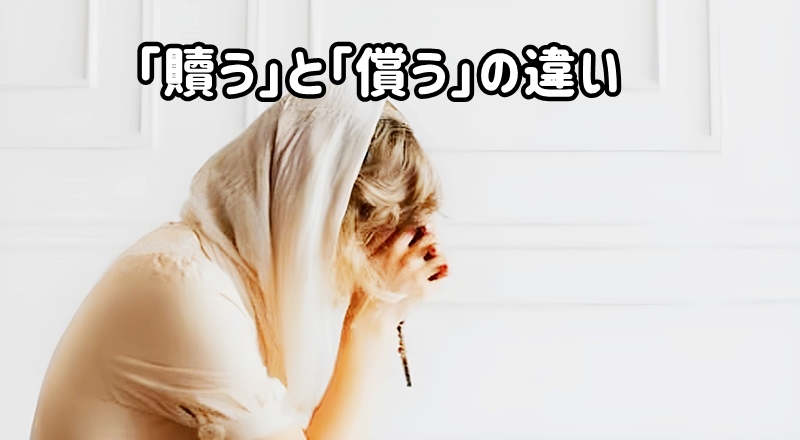
- 贖うは「あがなう」、償うは「つぐなう」と読む
- 贖うは「罪」に特化、償うは「一般的な損失・間違い」全般
- 宗教的文脈では贖うが使われることが多い
- 法的・日常的な場面では償うが適している
- キリスト教の「贖罪」は贖うの代表的な使用例
- 両者を正しく使い分けることで文章の質が向上する
- 贖う(あがなう)は「罪」に対する補償
- 償う(つぐなう)は「損失・間違い」全般に対する補償(現代は一般的に使用)
私も高校時代、国語のテストで「贖う(あがなう)」を「つぐなう」と読んで×をもらった経験があります。
実はこの2つの言葉、読み方も意味もまったく違うんです。
文学作品の読解や正式な文書作成で恥をかかないよう、しっかり理解しておきませんか?
贖うと償うの基本的な違い
読み方の違い
| 漢字 | 読み方 | 英語表記 |
|---|---|---|
| 贖う | あがなう | redeem |
| 償う | つぐなう | compensate |
「贖う」は「あがなう」と読み、「償う」は「つぐなう」と読みます。
多くの人が混同してしまう理由は、どちらも「罪や過ちを補償する」という似た意味を持つからです。

意味の違い
贖う(あがなう)の意味
罪のつぐないをする、特に金品を出して罪を免れることを指します。
宗教的な文脈では、罪ほろぼしをすることも意味します。
償う(つぐなう)の意味
間違いや損失を補うために行われる行為を指し、
相手に与えた損失や負債に対して金品で弁済することを意味します。
あなたは普段、どちらの言葉を使う機会が多いでしょうか?
現代社会では、この償う(つぐなう)が一般的に使用されています。
贖う(あがなう)の方は、現在は使用する場面があまりなく、ほとんど使用されません。
贖うの詳しい意味と使い方
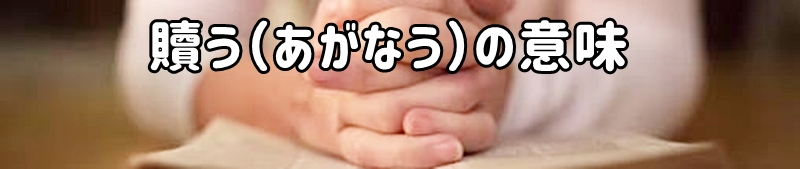
語源と成り立ち
「贖う」は古語の「あかう」から派生した言葉です。
「贖」という漢字には、刑罰を免れるために金品を差し出すという意味が込められています。
使用場面
- 宗教的文脈:キリスト教の贖罪(しょくざい)
- 文学作品:罪に対する精神的な償い
- 歴史的文書:古い時代の刑罰制度
具体的な使用例
- 「彼は過去の罪を贖うために慈善活動に励んだ」
- 「十字架のキリストが人々の罪を贖った」
- 「死をもって罪を贖う覚悟だった」
私の祖父は戦後、「戦争協力した罪を贖うため」と言って地域の復興に尽力していました。
この場合、単なる経済的補償ではなく、道徳的・精神的な罪に対する行為だったのです。
参考:コトバンク贖う
償うの詳しい意味と使い方
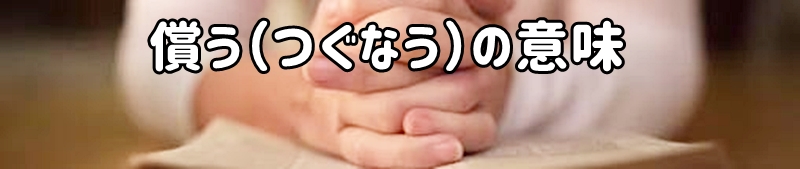
日常生活での頻度
「償う」は「贖う」よりも日常的に使われる言葉です。ニュースや法的文書でもよく目にしますね。
現代の社会では、ほとんどの場面で「償う」が使用されています。
使用場面
- 法的文書:損害賠償、責任の履行
- 日常会話:謝罪や弁償の表現
- ビジネス:契約違反への対応
具体的な使用例
- 「事故の損害を償う」
- 「借金を償い終えた」
- 「迷惑をかけた分を労働で償う」
とはいえ、使い分けに迷うことはありませんか?
参考:コトバンク償う
体験談:(40代・男性・会社員)
新人時代、大きなプロジェクトで発注ミスをし、数千万円の損失を出しました。
解雇も覚悟しましたが、上司は「償いはお金でできるが、信頼を取り戻すのは努力次第」と励ましてくれました。
それ以来、早出や熱心な働きで信頼を築き、数年後には大きな契約を獲得。上司から「努力がミスを贖った」と称賛され、行動と誠意の重要性を学びました。
使い分けのポイント
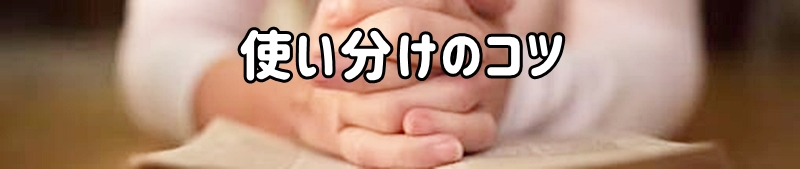
対象による分類
| 対象 | 使う言葉 | 理由 |
|---|---|---|
| 宗教的な罪 | 贖う | 精神的・道徳的な意味合い |
| 法的な責任 | 償う | 具体的な損害への対応 |
| 経済的損失 | 償う | 物質的な補償 |
| 道徳的過ち | 贖う | 罪の意識を伴う行為 |
文脈による判断基準
「贖う」を選ぶ場合
- 罪悪感を伴う深刻な過ち
- 宗教的・哲学的な文脈
- 文学的表現を求める場面
「償う」を選ぶ場合
- 具体的な損害がある場合
- 法的・経済的な文脈
- 日常的な謝罪や弁償
実のところ、現代日本では「償う」の方が圧倒的に使用頻度が高いです。
関連する重要な語彙
贖罪(しょくざい)の理解
贖罪とは「金品を出して罪を免れること」「罪ほろぼしをすること」「キリスト教の教義でキリストが十字架にかかり人々の罪をあがなったこと」を意味します。
購う(あがなう)との混同
「購う」も「あがなう」と読みますが、これは単に「買い求める」という意味です。文脈で判断する必要があります。
贖うと償うを含む熟語・慣用句
贖う系の表現
- 贖罪(しょくざい)
- 贖物(あがもの)
- 罪を贖う
償う系の表現
- 損害償却
- 償還(しょうかん)
- 代償(だいしょう)
ふと思うのですが、なぜこんなに似た言葉が存在するのでしょうか?
文学作品での使用例
贖うの文学的用法
文学作品では「贖う」がよく使われます。
主人公の心の葛藤や精神的成長を表現する際に効果的だからです。
教育現場での指導経験
私が塾で教えている生徒たちも、最初はこの区別に苦労します。
しかし「贖うは宗教的、償うは現実的」と覚えてもらうと、理解が早いようです。
- 贖うは宗教的
- 償うは現実的
実際に中学入試でも、この違いを問う問題が複数の学校で出題されています。
それほど重要な知識なのです。
かなり勉強しないと、間違いやすいです。

間違いやすい使用例とその訂正
よくある間違い
❌「事故の損害を贖う」 ⭕「事故の損害を償う」
❌「キリストの罪を償い」 ⭕「キリストの罪を贖い」
判断に迷う例文
「彼は過去の過ちを○○うため、毎日働いている」
この場合、過ちが道徳的・精神的なものなら「贖う」、具体的な損害なら「償う」を選びます。
- 道徳的・精神的なもの→贖う
- 具体的な損害なら→償う
さて、実生活でこれらの言葉を使う機会はあるでしょうか?
現代社会での使用頻度
メディアでの使用傾向
新聞記事では「償う」が圧倒的に多く使われています。
一方、宗教関連や文化的な記事では「贖う」が選ばれる傾向があります。
現代社会では、償うが一般的です。
ビジネス文書での注意点
契約書や正式な文書では、基本的に「償う」を使用します。
「贖う」は文学的すぎて、法的文書には適しません。
関連記事の解説
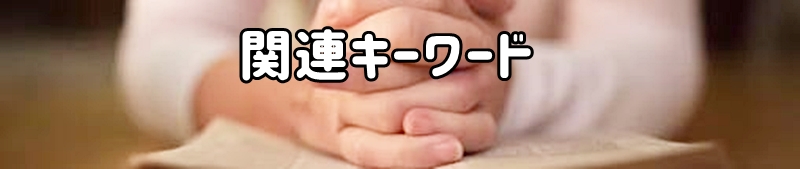
「贖うの読み方」について
「贖う」を「つぐなう」と読む人が多いのは、意味が似ているからです。
しかし、正しくは「あがなう」です。音読みでは「ショク」と読み、「贖罪(しょくざい)」という熟語で使われます。
漢字の形も「貝」偏があることから、金品に関わる意味を持つことが分かります。
古代中国では、罪を犯した際に金品を納めて刑罰を免れる制度があったため、この漢字が生まれました。
「償うの意味」について
「償う」は「つぐなう」と読み、相手に与えた損害や迷惑に対して埋め合わせをすることを意味します。
法的な責任を果たす場合や、日常的な謝罪の際に使われる一般的な言葉です。
語源は「つぐ(継ぐ)」と「なう(縄う)」から来ており、
欠けたものを補って元の状態に戻すという意味があります。
現代では経済的補償だけでなく、精神的な埋め合わせの意味でも使わるようになっています。
「贖うと償うの違いをわかりやすく」について
最も分かりやすい区別方法は、対象が「罪」か「損失・間違い」かを考えることです。
罪悪感を伴う深刻な過ちには「贖う」、具体的な損害や一般的な間違いには「償う」を使います。
また、宗教的・哲学的な文脈では「贖う」、法的・日常的な文脈では「償う」が適しています。
迷った時は「償う」を選んでおけば、現代日本では間違いありません。
「あがなう・つぐなう」について
「あがなう(贖う)」は罪に対する補償、「つぐなう(償う)」は損失に対する補償という違いがあります。
読み方だけでなく、使用場面も大きく異なります。
「あがなう」は文学的・宗教的な表現に多く、「つぐなう」は日常的・法的な表現に多用されます。
現代の文章では「つぐなう」の方が圧倒的に多く使われており、公式文書でも基本的に「償う」が選ばれます。
「贖うの英語」について
「贖う」の英語は主に「redeem」です。宗教的文脈では「atone」も使われます。
キリスト教の贖罪は「atonement」「redemption」と表現され、罪からの救済という意味が込められています。
ビジネスでは「compensate for」「make amends for」なども使われますが、
これらは「償う」の翻訳により近い表現です。
英語圏でも宗教的な「redeem」と一般的な「compensate」は明確に区別されています。
「贖うの使い方」について
「贖う」は主に文学作品や宗教的な文章で使われます。
日常会話ではあまり使いませんが、深刻な道徳的過ちについて語る際に効果的です。
使用例として「過去の罪を贖うため」「十字架で罪を贖った」「死をもって贖う」などがあります。
現代の小説や映画でも、主人公の精神的成長を表現する際によく使われる表現です。
ただし、軽い謝罪には使わず、重大な罪に対してのみ使用します。
「償うの例文」について
「償う」の例文は日常的なものから法的なものまで幅広くあります。
「事故の損害を償う」「借金を償い終える」「迷惑をかけた分を労働で償う」「責任を償う義務がある」などです。
ビジネス文書では「損失を償う」「契約違反を償う」といった表現が一般的です。
日常会話では「お詫びの気持ちを償わせてください」のような丁寧な謝罪にも使われます。
法的文書では必ず「償う」を使い、「贖う」は使用しません。
よくある質問(FAQ)
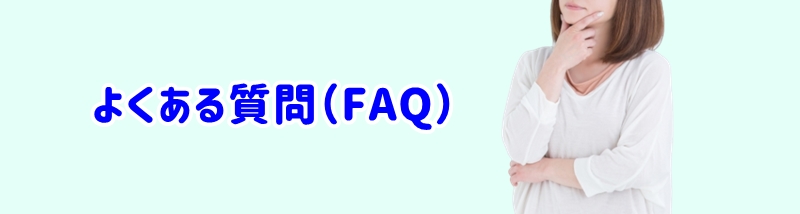
Q1: 「贖う」と「償う」はどちらを使えば間違いない?
A1: 迷った場合は「償う」を選んでください。現代日本では「償う」の方が一般的で、
日常的な場面から法的な場面まで幅広く使えます。
「贖う」は宗教的・文学的な特殊な文脈でのみ使用される言葉です。
Q2: 宗教に関係ない場面でも「贖う」は使える?
A2: はい、使えます。深刻な道徳的過ちや罪悪感を伴う行為について語る際は、
宗教的でない文脈でも「贖う」が適切です。
ただし、文学的な響きがあるため、日常会話よりも書き言葉で使用されることが多いです。
Q3: 「購う」も「あがなう」と読むが、どう区別する?
A3: 文脈で判断します。「購う」は単純に「買う」という意味で、罪や補償の意味はありません。
現代では「購入」「購買」の形で使われることがほとんどです。
Q4: 法的文書ではどちらを使うべき?
A4: 法的文書では必ず「償う」を使用してください。
「贖う」は文学的すぎて、契約書や公式文書には適しません。
損害賠償、責任履行などの法的概念には「償う」が正しい選択です。
Q5: 子どもにはどう教えれば良い?
A5: 「贖うは宗教や文学の世界、償うは現実の世界」と覚えさせると効果的です。
また、「贖うはあがなう、償うはつぐなう」という読み方の違いから入ると理解しやすいでしょう。
Q6: 敬語表現で使う場合の注意点は?
A6: どちらも丁寧語「~ます」をつけて使用できますが、「償う」の方が一般的です。
「お詫びの意味を込めて償わせていただきます」のような表現が適切です。
まとめ
「贖う」と「償う」の違いを理解することで、より正確で豊かな日本語表現が可能になります。
現代社会では「償う」の使用頻度が高いものの、文学作品や宗教的文脈では「贖う」が重要な役割を果たします。
読み方から使い分けまで、この記事で解説したポイントを押さえて、
適切な言葉選びができるようになりませんか?
正しい日本語の使い方は、あなたの教養と品格を表現する大切な要素なのです。
記事の要点まとめ
- 贖うは「あがなう」と読み、罪に特化した補償を意味する
- 償うは「つぐなう」と読み、一般的な損失・間違いの補償を意味する
- 宗教的・文学的文脈では贖う、法的・日常的文脈では償うを使用
- 迷った場合は現代では償うを選ぶのが無難
- 贖罪はキリスト教の重要な概念で贖うの代表例
- 両者の正しい使い分けで日本語の表現力が向上する
- 法的文書では必ず償うを使用し贖うは避ける
- 購うも「あがなう」と読むが単純に買うという意味
- 読み方の違いが意味の違いを反映している
- 文学作品では贖うがよく使われ心の葛藤を表現
- 教育現場でも頻出の重要な言葉の区別
- 正しい理解で品格のある日本語表現が可能になる

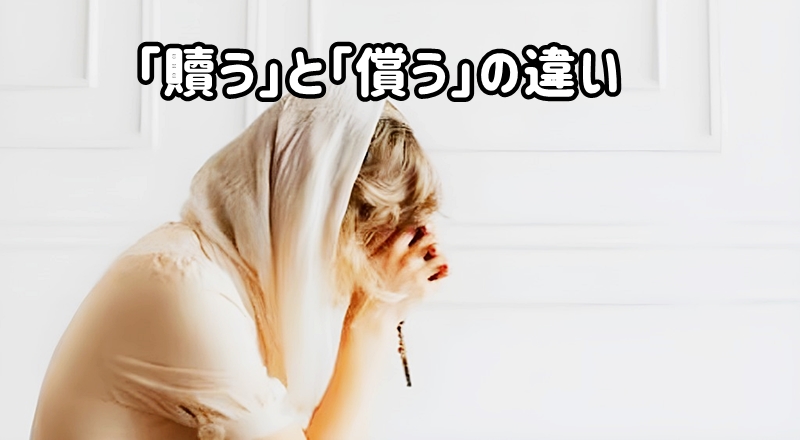
コメント