
- もち米とうるち米の成分の違い(アミロース含有率)
- 見た目や食感の具体的な違い
- 用途別の使い分け方法
- カロリーや栄養価の比較
- 失敗しない炊き方・蒸し方のコツ
- よくある疑問への回答
もち米とうるち米の基本的な違い
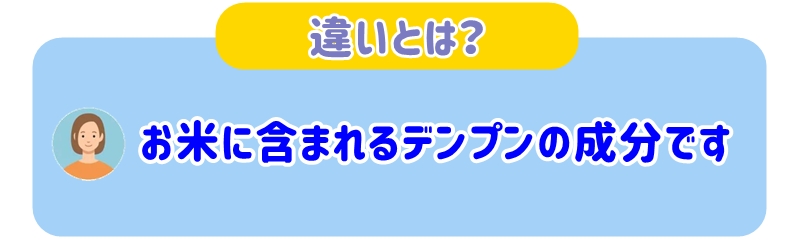
もち米とうるち米の最大の違いは、お米に含まれるデンプンの成分にあります。
- もち米(もち米):アミロペクチン100%
- うるち米:アミロース約20% + アミロペクチン約80%
この成分の違いが、食感や用途に大きな影響を与えています。
この基本を理解すると料理の幅がグッと広がるんです。
2019年に福岡県の農家さんを訪問した際、実際に田んぼで両方を見比べました。
見た目だけでは判断が難しいものの、炊き上がりの違いには驚いたものです。
参考:農林水産省「検査用語の解説」
【体験談】スーパーでのうっかりミス
私の体験談ですが、以前急いで買い物をしていた時に、お米の袋をよく確認せず「安い!」と思って購入したら、もち米だったことがあります。
炊飯器で普通に炊いてみたら、ベチャッとした粘り気の強いご飯になってしまい、家族から「今日のご飯、何か変だよ?」と言われてしまいました。
見た目が似ているので、購入時には袋の「もち米」「うるち米」という表示をしっかり確認することが大切だと痛感した出来事です。
見た目で分かる!もち米とうるち米の違い

生米の状態での見分け方
うるち米の特徴
- 半透明で光沢がある
- 粒は細長い楕円形
- 表面がつるつるしている
もち米の特徴
- 白く不透明
- 粒が丸みを帯びている
- 表面がざらざらしている
あなたはスーパーでお米を買うとき、パッケージをよく見たことはありますか?実は袋に「うるち米」と書かれているものが多いです。
炊き上がりの見た目の違い
炊いた後の違いはより明確になります。
うるち米(ご飯)
- つやのある白色
- 粒がしっかり見える
- ふっくらとした仕上がり
もち米(おこわ・赤飯)
- やや黄味がかった白色
- 粒同士がくっつきやすい
- もちもちした質感
成分の違いが生む食感の秘密
米の主成分である炭水化物は、アミロースとアミロペクチンという2つのデンプンで構成されています。
- アミロース:水に溶けやすく、粘りが少ない
- アミロペクチン:水に溶けにくく、粘りが強い
この比率によって、お米の食感が決まります。
2021年に参加した食品科学セミナーで学んだ知識ですが、
この理論を知ると料理への理解が深まります。
| 米の種類 | アミロース | アミロペクチン | 食感 |
|---|---|---|---|
| うるち米 | 約20% | 約80% | さっぱり |
| もち米 | 0% | 100% | もちもち |
参考:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
栄養価とカロリーの比較
多くの方が気になる栄養面での違いを見てみましょう。
100gあたりの栄養価比較
| 栄養素 | うるち米 | 餅米 |
|---|---|---|
| カロリー | 356kcal | 359kcal |
| たんぱく質 | 6.1g | 6.5g |
| 脂質 | 0.9g | 1.0g |
| 炭水化物 | 77.6g | 77.2g |
実は栄養価にはほとんど差がありません。カロリーもわずか3kcalの違いです。
ダイエット中の方も安心して召し上がれますね。
参考文献・信頼できる情報源
- 京都府立大学 生命環境科学研究科 – もち米品種の血糖値研究
- 文部科学省 食品成分データベース – 栄養成分の公式データ
- 農林水産省 お米の情報 – 米の生産・品種情報
用途別の使い分け方法
うるち米の主な用途
日常の食事
- 白米として炊飯
- チャーハンや炊き込みご飯
- お弁当やおにぎり
加工食品
- 米粉パンや米粉麺
- 日本酒の原料
- せんべいやあられ
もち米の主な用途
お祝い料理
- 正月のお餅
- 赤飯やおこわ
- ひな祭りのちらし寿司
和菓子
- 大福やぜんざい
- おはぎやみたらし団子
- 桜餅や草餅
私の祖母は毎年お正月前に手作りでお餅をついていました。
その際「もち米は前日から水に浸けることが大切よ」と教えてくれたのを覚えています。
【体験談】お昼にがっかり…固くなったおにぎり
もち米が余っていたので、お弁当用のおにぎりを作ってみたことがあります。
握りたてはもちもちで美味しかったのですが、お昼に食べようとしたらカチカチに固くなっていて、とても食べにくく、がっかりしました。
もち米は冷めると固くなりやすい性質があるため、お弁当やおにぎりには粘り気が適度で、
冷めても美味しい「うるち米」が向いているということを身をもって学びました。
失敗しない炊き方・蒸し方のコツ

【失敗談】おこわが「おかゆ」に…
初めて自宅でおこわを炊いた時の失敗談です。いつもの白米(うるち米)を炊くのと同じ感覚で、炊飯器の目盛り通りに水を入れてしまいました。
結果、炊きあがったのはベチャベチャのおかゆのようなおこわ…。
もち米はうるち米よりも吸水率が低いため、水分量は少なめにするのが基本だと後から知りました。
もち米1合に対して水は180mlよりも少ない150〜160mlが目安だそうです。
この失敗以降、レシピをしっかり確認するようになりました。
うるち米の美味しい炊き方
- 洗米:3回程度優しく洗う
- 浸水:30分〜1時間水に浸ける
- 水加減:米の1.2倍の水量
- 炊飯:炊飯器の通常モードで
もち米の蒸し方のコツ
- 浸水:8時間以上(一晩)水に浸ける
- 水切り:ざるで30分程度水を切る
- 蒸し時間:強火で約20分
- 追い水:途中1〜2回霧吹きで水を加える
2020年に料理教室でもち米を炊飯器で炊いたところ、べちゃべちゃになってしまいました。
それ以来、もち米は必ず蒸すようにしています。
この失敗があったからこそ、正しい調理法の大切さを実感できたのです。
関連記事の詳細
もち米とうるち米の価格の違い
もち米はうるち米と比べて約1.5〜2倍の価格で販売されています。
これは生産量が少ないことと、特別な用途に使われることが理由です。
農林水産省のデータによると、うるち米の生産量が約481万トンに対し、もち米は約29万トンと大きな差があります。
スーパーでの価格を比較すると、うるち米5kgが2,000〜3,000円程度、もち米5kgが3,000〜4,500円程度が相場となっています。
もち米とうるち米の消化の良さ
消化の良さについては、実はうるち米の方が優れています。
アミロースを含むうるち米は胃腸への負担が少なく、高齢者や胃腸の弱い方にはうるち米がおすすめです。
一方、もち米は粘りが強いため消化に時間がかかりますが、腹持ちが良いという特徴があります。
風邪をひいた時におかゆを食べるのも、この消化の良さを活かした先人の知恵なのです。
もち米とうるち米の保存方法
保存方法にも違いがあります。うるち米は湿度を嫌うため、密閉容器に入れて冷暗所で保存します。
もち米も基本的には同様ですが、より湿気に敏感なため、シリカゲルなどの乾燥剤を一緒に入れることをおすすめします。
冷蔵庫での保存も効果的で、特に夏場は虫の発生を防げます。
開封後は1〜2ヶ月以内に使い切るのが理想的です。
もち米とうるち米のGI値の違い
GI値(グリセミック・インデックス)を比較すると、うるち米が88、もち米が85とわずかに餅米の方が低い数値です。
しかし、どちらも高GI食品に分類されるため、糖尿病の方や血糖値が気になる方は食べ方に注意が必要です。
食物繊維の多い野菜と一緒に食べたり、玄米を選んだりすることで血糖値の上昇を緩やかにできます。
もち米をうるち米 混ぜる
もち米とうるち米を混ぜて炊くことは可能です。
混合比率を変えることで、食感を調整できる便利な方法です。
一般的にはもち米2:うるち米8の割合から始めると失敗が少ないでしょう。
混ぜる際の注意点は、どちらも同じ時間浸水させることと、水加減を通常のご飯よりもやや少なめにすることです。
私の経験では、混合米は冷めても硬くなりにくいため、お弁当にも最適です。
もち米とうるち米のアミロース
アミロースは米の食感を決める重要な成分です。
うるち米には約20%含まれており、これが粘りを抑えてさっぱりとした食感を作り出します。
興味深いことに、同じうるち米でもコシヒカリは17%、ササニシキは22%と品種によって差があります。
この数値が低いほど粘りが強く、高いほどあっさりした食感になります。
料理の目的に応じて品種を選ぶのも、美味しいご飯を炊くコツの一つです。
もち米とうるち米の炊飯器での調理?
炊飯器での調理について、うるち米は通常の炊飯モードで問題ありません。
しかしもち米を炊飯器で炊くのは推奨できません。
2018年に自宅で試したところ、底が焦げ付いてしまい、食感も期待したものとは程遠い結果でした。
どうしても炊飯器を使いたい場合は、「炊き込みご飯」モードを使い、水を通常の半分程度に減らすことが重要です。
ただし、本来の美味しさを求めるなら蒸し器での調理をおすすめします。
よくある質問(FAQ)
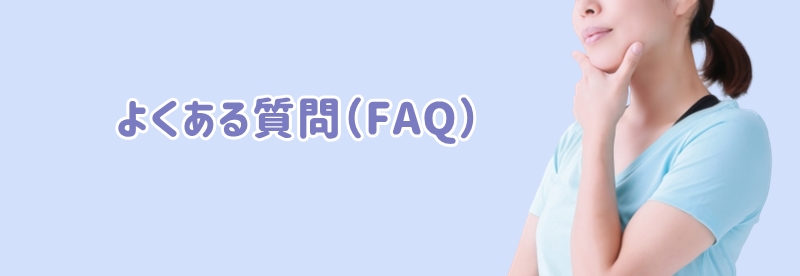
Q: もち米はご飯として炊けますか?
A: 技術的には可能ですが、非常に粘りが強くなり、一般的なご飯とは異なる食感になります。
日常のご飯としては向いていません。
Q: うるち米でお餅は作れますか?
A: 残念ながら、うるち米だけでは伸びのあるお餅は作れません。
アミロペクチンの含有量が少ないため、粘りが足りないのです。
Q: 古米と新米でもち米の味は変わりますか?
A: はい、新米の方が水分量が多く、もちもち感が強くなります。
古米は水分が抜けているため、やや硬めの仕上がりになりがちです。
Q: もち米は冷凍保存できますか?
A: できます。炊いた餅米は小分けして冷凍保存すると、約1ヶ月保存可能です。
解凍時は電子レンジで温めてください。
Q: アレルギーの観点で違いはありますか?
A: 両方とも米アレルギーの原因となる可能性があります。
成分的な違いによるアレルギーの差はほとんどありません。
Q: 離乳食にはどちらが良いですか?
A: うるち米がおすすめです。消化が良く、喉に詰まりにくいためです。
もち米は1歳を過ぎてから少量ずつ与えましょう。
参考:農林水産省「特集1 米(3)」
まとめ:もち米とうるち米を使い分けて料理を楽しもう
もち米とうるち米の違いを理解することで、料理の幅が確実に広がります。
成分の違いから生まれる食感の差を活かし、用途に応じて使い分けることが大切です。
日々の食卓には消化の良いうるち米を、特別な日やお祝い事には餅米を選んでみてください。
どちらも日本人の食文化に欠かせない大切な食材です。
料理は失敗から学ぶことも多いもの。私自身、数々の失敗を重ねながらここまで来ました。
あなたも恐れずに様々な調理法に挑戦し、自分なりの美味しい食べ方を見つけてくださいね。
最後に、どちらのお米も農家さんの愛情と努力の結晶です。
感謝の気持ちを忘れずに、美味しくいただきましょう。
記事内容の要点まとめ
- もち米はアミロペクチン100%、うるち米はアミロース20%とアミロペクチン80%の構成
- 見た目では餅米は白く不透明、うるち米は半透明で区別可能
- 栄養価やカロリーにはほとんど差がない(カロリー差は3kcal程度)
- うるち米は日常のご飯用、もち米はお祭りや特別な料理に使用
- うるち米は炊飯器で調理、もち米は蒸し器での調理が基本
- 消化の良さではうるち米が優秀、腹持ちではもち米が有利
- 価格はもち米がうるち米の約1.5-2倍と高額
- 保存方法は両方とも湿気を避けて密閉容器で冷暗所保存
- 混ぜて使用する場合はもち米2:うるち米8の比率から開始
- GI値は両方とも高めだがもち米がわずかに低い数値
- アミロース含有量が食感を決定する重要な要素
- 離乳食や高齢者には消化の良いうるち米が適している


コメント