
- はさみの数え方は「本」が現代では一般的
- 正式な数え方は「挺(てい)」「丁(ちょう)」
- 英語では「a pair of scissors」と表現する
- シーンによって適切な使い分けが必要
- 他の刃物との数え方の違いがわかる
- 間違いやすいポイントと注意点を解説
はさみの数え方は「1本、2本」が現代では最も一般的です。
しかし、正式には「1挺(てい)、2挺」「1丁(ちょう)、2丁」が正しい数え方とされています。
私は文具店で勤務していた経験がありますが、
お客様に「はさみ何本ありますか?」と聞かれることが多く、
実際の現場でも「本」が主流でした。
ただし、書道具専門店では「1挺(てい)のはさみ」と表現されることがあり、
場面による使い分けが大切だと学びました。
はさみの数え方の基本
現代で最も使われる数え方:「本」
現在、はさみの数え方として最も一般的に使用されているのは「本」です。
日常会話や学校、オフィスなどで「はさみ2本貸して」「はさみ1本ください」と表現することが多いでしょう。
「本」を使う理由
- はさみの形が細長いため
- 他の文房具(ペン、鉛筆など)と同じ単位で統一
- 理解しやすく、コミュニケーションが円滑
正式な数え方:「挺(てい)」「丁(ちょう)」
一般的には1本と言いますが、専門的な業界などの人は1丁と言います。
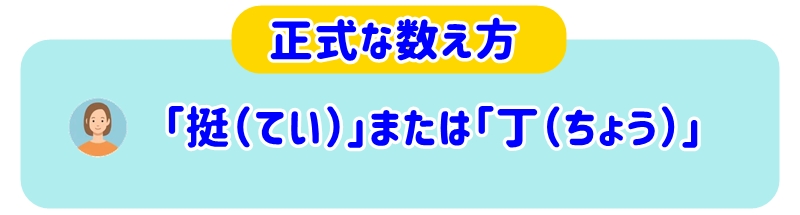
はさみの正式な数え方は「挺(てい)」または「丁(ちょう)」です。
これらは古くから刃物や道具を数える際に使用されてきた助数詞です。
読み方のポイント
- 挺:「てい」または「ちょう」
- 丁:「ちょう」または「てい」
- どちらも同じ意味で使用可能
私が茶道を習っていた際、師匠から「菓子切り1挺をお持ちください」と言われたことがあります。
その時、単に道具を指すのではなく、丁寧に扱うべき大切なものという意味が込められていると感じました。
はさみの種類別数え方一覧表
| はさみの種類 | 一般的な数え方 | 正式な数え方 | 使用場面 |
|---|---|---|---|
| 文房具はさみ | 1本、2本 | 1ちょう、2ちょう | 学校、オフィス |
| 裁ちばさみ | 1本、2本 | 1ちょう、2ちょう | 手芸、洋裁 |
| 散髪ばさみ | 1本、2本 | 1ちょう、2ちょう | 美容室、理容室 |
| 剪定ばさみ | 1本、2本 | 1ちょう、2ちょう | 園芸、造園 |
| 工作はさみ | 1本、2本 | 1ちょう、2ちょう | 工作、図工 |
よくある間違いと正しい使い方
間違いやすいポイント
❌ よくある間違い
- 「はさみ1個ください」
- 「はさみ1つ持ってきて」
- 「はさみ1枚使います」
⭕ 正しい表現
- 「はさみ1本ください」
- 「はさみ1挺お持ちください」(フォーマル)
あなたも無意識に「はさみ1個」と言ってしまったことはありませんか?
私も以前は「1個」と言っていましたが、正しい数え方を知ってから意識するようになりました。
他の刃物との数え方比較
包丁の数え方
包丁は「本」または「挺」で数えます。料理人の世界では「1挺の包丁」と表現することが多いです。
使い分け例
- 家庭:包丁1本
- 料理の現場:包丁1挺
カッターの数え方
カッターナイフは「本」で数えるのが一般的です。「カッター1本」「カッター2本」と表現します。
ナイフの数え方
ナイフは「本」で数えることが最も一般的です。「ナイフ1本」と表現します。
シーン別使い分けガイド
日常生活での使い方
家庭や学校では「本」を使用すれば問題ありません。「はさみ1本取って」「はさみ2本必要」など、自然に使えます。
ビジネスシーンでの使い方
オフィスでは「本」で十分ですが、お客様との会話や正式な文書では「挺」を使用するとより丁寧な印象を与えます。
専門分野での使い方
- 美容師:「はさみ1挺」(道具への敬意を表現)
- 職人:「道具1挺」(伝統的な表現)
- 書道:「筆1本、はさみ1挺」(格式を重視)
私が書道教室に通っていた時、先生は必ず「はさみ1挺」と言われていました。
単なる道具ではなく、大切に扱うべきものという気持ちが伝わってきました。
はさみの数え方の歴史と由来
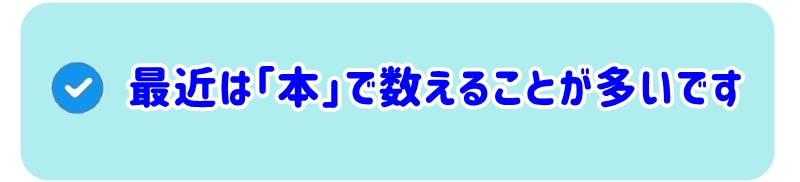
はさみの数え方には興味深い歴史的な変遷があります。かつてははさみは「挺(丁)」で数えられていましたが、最近では「本」で数えることが多くなっています。
参考: Sanabo
「丁」「挺」の由来
「丁」「挺」は、もともと真っ直ぐな棒を表す言葉でした 。
それがいつしか手に持つ道具一般を数えるのに使われるようになり、刃物、銃、弓などの武器から鋤、鍬などの農具、金槌などの工具、バイオリン、ギターなどの楽器まで、その用途はかなり広範に及んでいます。
数え方の変化
時代とともに、はさみの数え方は変化してきました。伝統的な「丁」「挺」という数え方は、道具としての格式や専門性を表す表現として用いられてきましたが、
日常生活では次第に「本」という、より一般的で分かりやすい数え方が普及してきました。
現代での使い分け
現在では用途や場面によって使い分けられています。日常会話や一般的な場面では「本」が主流となっていますが、専門的な場面や伝統的な文脈では「丁」「挺」が使われることもあります。
ただし「挺」は常用漢字ではないため、代用字として「丁」が用いられることが多くなっています。
このように、はさみの数え方には、日本語の助数詞の歴史的変遷と、実用性を重視する現代的な傾向が反映されているといえるでしょう。
関連記事の解説
はさみの漢字表記について
はさみは「鋏」「剪刀」と漢字で表記されます。
「鋏」が最も一般的で、金属を意味する「金」偏が使われています。
この漢字を見ると、なぜ「挺」で数えるのかが理解できますね。
古来から金属製の道具として大切に扱われてきた証拠でしょう。
はさみの正しい持ち方と数え方の関係
はさみを正しく持つ時、親指と人差し指で握る部分が「柄」と呼ばれます。
この柄が1本の道具として認識されるため、「1本」「1挺」という数え方になったと考えられています。
地域による数え方の違い
関西地方では「挺」を使う傾向が関東より強く、
職人の世界では今でも「1挺、2挺」と数えることが多いです。
一方、関東では「本」が主流となっています。
方言というほどではありませんが、微妙な地域差があるのも興味深いですね。
実践的な使い方のコツ
迷った時の判断基準
どの数え方を使うか迷った時は、以下を参考にしてください:
「本」を選ぶとき
- 日常会話
- カジュアルな場面
- 相手が子どもの場合
- 急いでいる時
「挺」を選ぶとき
- フォーマルな場面
- 年上の方との会話
- 伝統的な場面
- 品質の良いはさみを指す時
自然な会話での使い方
「はさみ借りるね」「はさみ1本貸して」など、短い表現では「本」が自然です。
「はさみを1挺お借りできますでしょうか」は丁寧ですが、日常会話では少し堅い印象になります。
よくある質問(FAQ)
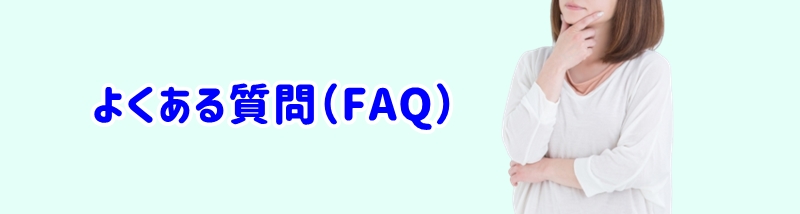
Q1. 子どもにはどちらを教えるべきですか?
A1. 小学生には「本」から教えることをおすすめします。
理解しやすく、他の文房具と同じ単位で覚えやすいためです。
中学生以降で「挺」も紹介すると良いでしょう。
Q2. ビジネスメールではどちらを使うべきですか?
A2. ビジネスメールでは「本」で問題ありません。
ただし、伝統工芸や高級品を扱う業界では「挺」を使用することで、
より専門性や敬意を示せます。
Q3. 複数のはさみをセットで売る時の数え方は?
A3. セット販売の場合は「組」を使用します。
「はさみ3本組」「裁縫はさみ5本セット」のように表現できます。
Q4. 外国人に説明する時のポイントは?
A4. 「Most people say “hon” (本), but formally we say “cho” or “tei” (挺/丁)」と説明すると理解してもらいやすいです。
Q5. 方言や地域差はありますか?
A5. 大きな方言はありませんが、職人の多い地域や伝統工芸が盛んな地域では「挺」を使う傾向があります。
まとめ:はさみの数え方マスターへの道
はさみの数え方について詳しく解説してきました。
現代では「本」が最も一般的ですが、「挺」「丁」が正式な数え方であることも覚えておきましょう。
重要なポイント
- 日常では「本」、フォーマルでは「挺」
- 相手や状況に応じた使い分けが大切
- 英語では「a pair of scissors」
- 他の刃物とは数え方が微妙に異なる
- 地域や職業によって好まれる表現が違う
最後に、私の失敗談をお話しします。
以前、高級文具店でお客様に「はさみ1本いかがですか?」と声をかけた際、
「この価格のはさみを『本』で数えるのは失礼では?」と指摘されました。
その日から、商品の価値や お客様の気持ちに配慮した言葉選びの大切さを実感しています。
あなたも場面に応じて適切な数え方を選択し、
相手に配慮したコミュニケーションを心がけてみてください。
正しい数え方を知っていることで、より豊かな日本語表現ができるようになるでしょう。
はさみの数え方を通じて、日本語の奥深さや美しさを改めて感じていただけたなら幸いです。
日常の小さな発見が、言葉への興味や関心を深めるきっかけになることもありますからね。
記事のまとめ
- はさみの数え方は「本」が現代では最も一般的で理解しやすい
- 正式な数え方は「挺(てい)」「丁(ちょう)」で伝統的な表現
- 英語では「a pair of scissors」と2枚の刃を意識した表現
- 種類に関係なく全てのはさみで同じ数え方を使用する
- ビジネスでは「本」、フォーマルでは「挺」の使い分けが重要
- 包丁やナイフなど他の刃物との数え方の違いを理解する
- 地域や職業によって好まれる表現に微妙な差がある
- 子どもには「本」から教えて段階的に「挺」を紹介する
- セット販売では「組」を使用して商品特性を表現する
- 相手への配慮と状況判断が適切な数え方選択のカギとなる


コメント