
「醤油って、何群なの?」
私自身、栄養学を学ぶ中でこの疑問に何度もぶつかり、
現場で料理を教える際もよく質問されます。
この記事では、醤油が何群に分類されるのかを徹底解説し、
さらに醤油の種類・使い分け・健康面の注意点まで、
他にはない現場の知見や失敗談も交えてお届けします。
- 醤油は何群に分類されるのか詳しく知りたい
- 6つの食品群と4つの食品群で醤油の位置づけはどう違うか
- 醤油がタンパク質群に属する理由とその栄養価について解説
- 料理に使う際、醤油をどの食品群として意識すれば良いか
- 醤油を健康的に活用するための注意点や摂取量について教えて
醤油は何群?【結論と理由】
食品群とは、食品の特徴に基づいて食品を分類したものです。
代表的なものに、栄養素の働きごとに分類される「6つの基礎食品群」や、
栄養素のバランスを考慮した「4つの食品群」などがあります。
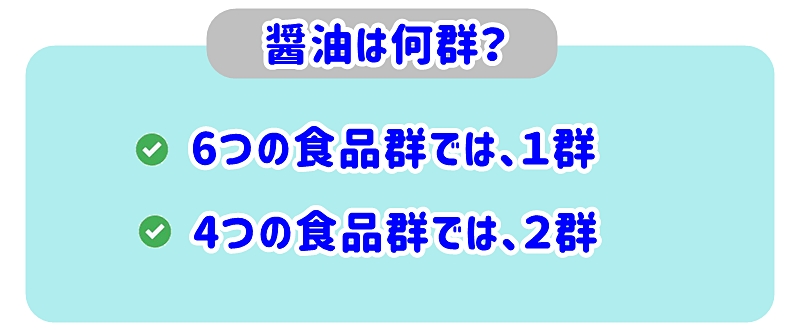
6つで分けた食品群での分類
醤油は6つの食品群では「1群」に分類されます。
6つの食品群は、栄養素の働きをわかりやすくするために作られた分類です。
1群は「タンパク質」を多く含む食品群になります。
醤油は大豆由来の植物性タンパク質やアミノ酸を含むため1群です。
4つで分けた食品群での分類
4つの食品群では「2群」に分類されます。
4つの食品群は、すべての食品を4群にまとめ、
栄養バランスを整えることをねらった実践的な方法です。
3色食品群では?
6つの基礎食品群
厚生労働省が示したもので、栄養素の働きをわかりやすくするため食品を1群から6群に分類しています。
| 群名 | はたらき | 食品 |
|---|---|---|
| 1群 | 骨や筋肉などをつくるエネルギー源となる | 魚、肉、卵、大豆、大豆製品 |
| 2群 | 骨・歯をつくる からだの各機能を調節 | 牛乳、乳製品、海草、小魚類 |
| 3群 | 皮膚や粘膜の保護 からだの各機能を調節 | 緑黄色野菜 |
| 4群 | からだの各機能を調節 | 淡色野菜、果物 |
| 5群 | エネルギー源となる からだの各機能を調節 | 穀類、いも類、砂糖 |
| 6群 | エネルギー源となる | 油脂類、脂肪の多い食品 |
4つの食品群
栄養素を意識しやすいように、食品を大きく4つに分類しています。
| 群名 | はたらき | 食品 |
|---|---|---|
| 1群 | 栄養を完全にする | 乳・乳製品 卵 |
| 2群 | 肉や血を作る | 魚介 肉 豆・豆製品 |
| 3群 | 体の調子を良くする | 野菜 いも 果物 |
| 4群 | 力や体温となる | 穀物 油脂 砂糖 |
醤油は何からできているの?
醤油は主に「大豆」「小麦」「塩(食塩)」の3つの原材料から作られています。
さらに、発酵と熟成の過程で「麹菌(こうじきん)」が使われることも重要なポイントです。

- 大豆:旨のもとの味となるタンパク質を含み、発酵中にアミノ酸へ分解されて醤油のコクや代替が生まれます。
- 小麦:憧れや香ばしさを加えて、醤油特有の風味を楽しめます。
- 塩:発酵をコントロールし、保存性を保つために使われます。
- 水:発酵を進めるために必要です。
- 麹菌:大豆と小麦を分解し、旨味や香りが出ます。
これらの原材料を使いこなす「麹づくり」「発酵・熟成」「圧搾」「加熱処理」といった工程を経て醤油が完成します。
醤油の種類と分類の違い

JAS規格の5種類
- 濃口醤油:日本の約8割を占める標準的な醤油
- 淡口醤油:色は淡いが塩分はやや高め、西日本で人気
- たまり醤油:とろみと旨味が強く刺身や照り焼きに最適
- 再仕込み醤油:濃厚で甘みがあり高級料理向き
- 白醤油:色が薄く、素材の色を活かしたい料理に
製法や等級による違い
醤油のメリット・デメリットと健康面

メリット
デメリット・注意点
醤油の上手な使い方と調理例

料理別おすすめ醤油
| 料理例 | おすすめ醤油 | 理由・ポイント |
|---|---|---|
| 刺身 | たまり醤油 | 旨味が濃く、色が美しい |
| 煮物 | 濃口醤油 | バランスの良い風味 |
| 吸い物・茶碗蒸し | 白醤油 | 素材の色を活かせる |
| 炒め物 | 淡口醤油 | 塩味が効き、色が淡い |
| 冷奴・焼き魚 | 醤油スプレー | 減塩&風味調整が簡単 |
現場での失敗談とアドバイス
私が料理教室でよく見かけるのは、「淡口醤油=塩分が薄い」と誤解して使い過ぎてしまうケース。
淡口は色が淡いだけで塩分は高めなので、使いすぎるとしょっぱくなりがちです。
逆に、たまり醤油は旨味が強いので少量でも十分。
用途に合わせて使い分けることで、料理の完成度が格段に上がります。
醤油は味噌と同じ仲間?
答えは「発酵食品としては仲間ですが、異なる点も多い」です。
共通点
- 主原料
どちらも大豆を主原料としています。 - 発酵
麹菌の働きによって発酵・熟成させて作られる「発酵食品」です。
相違点
- 麹菌の種類
醤油は主に「醤油麹菌(アスペルギルス・ソーエ)」、味噌は主に「味噌麹菌(アスペルギルス・オリゼー)」が使われます。 - 製造工程
醤油は発酵・熟成させた「もろみ」を搾って液体にします。一方、味噌は蒸した大豆と麹、塩を混ぜてペースト状のまま熟成させます。 - 栄養
味噌は搾らずに大豆を丸ごと使うため、食物繊維やたんぱく質が醤油よりも豊富に含まれています。
同じ大豆から作られる発酵食品でも、これだけの違いがあるのは面白いですね。
料理によって醤油と味噌を使い分けることで、味のバリエーションは無限に広がります。
醤油はなぜ黒いの?
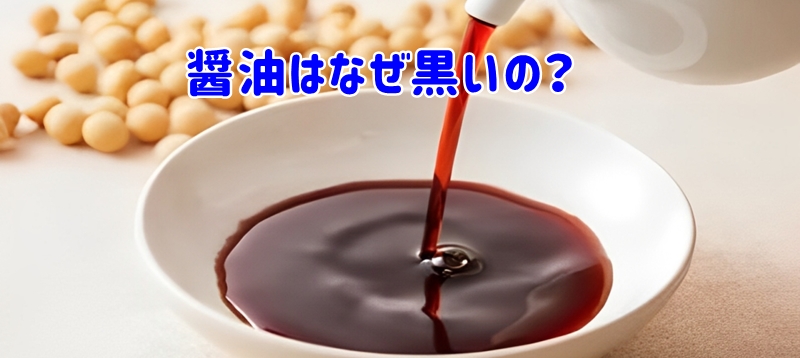
醤油が黒いのは、原料となるや小麦、塩を発酵させる過程で「メイラード反応」という化学反応が起き、
発酵の過程では、こうじ菌が分解したアミノ酸と糖が反応してメイラード反応が起こり、
この現象によって醤油特有の黒い色や香ばしい風味が生まれます。
また、保存中に酸素や光、温度の影響で酸化が進むことでもさらに色が黒ずむことがあります。
つまり、醤油の黒さは発酵による自然な化学反応と、その後の酸化の影響によるものです。
醤油の発祥の地はどこ?
日本醤油の発祥の地は、和歌山県湯浅町(紀州され湯浅)とされています。

ここで中国から来た味噌の製法から、味噌の上澄み液を改良して最新の醤油が生まれました。
歴史的な経緯として、鎌倉時代に禅僧覚心(かくしん)が
中国の宋から径山寺味噌(けいざじみそ)の製法を伝え、
和歌山県湯浅町で作った味噌の桶に溜まる上澄み液を調味料として改良したのが
日本の醤油の起源とされています。
ただし、醤油のルーツ自体はさらに古代中国の「醤(ジャン)」に至るまで行われて、
日本独自の発展を極めた調味料であると言えます。
醤油は何性?
醤油(しょうゆ)は弱酸性の液体調味料であり、一般的なpH値は4.7~5.0前後です。
この値は多くの日本メーカーや専門団体からも示されていて、
発酵過程で乳酸や酢酸といった有機酸が主な酸味成分となっています。
- pHの分類では、pH7が中性、7より低ければ酸性、7より高ければアルカリ性です。
醤油のpHは5前後であるため、明確に酸性の範囲に入りますが、その中でも「弱酸性」と呼ばれます。 - 味の角まえ:醤油に多く含まれる乳酸は塩味の角をミックス、味をまろやかに仕上げる効果があります。
- おいしさとの関係:人間はpH4~5程度の食べ物を「最もおいしい」と感じやすく、
醤油のpHがこれに気づくことが食材の味をよくする理由の一つとされています。。
やはり、醤油はpH4.7~5.0の弱酸性の調味料であり、
その性質が味覚のバランスや食材との相性を決める重要な要素となっています。
醤油の江戸時代は?
江戸時代の醤油は、日本の食文化と産業に大きな変革をもたらした調味料です。
江戸時代初期には、主に関西(上方)で作られた「下り醤油」(たまり醤油や澄み醤油)が
高価な感動品として江戸に盛り上がっていましたが、
1700年代以降、関東地方で江戸の好みに合わせた「濃口醤油」が発展し、
- 江戸時代初期、江戸で主に消費されていたのは和歌山や大阪など西日本産の下り醤油でした。
- 17世紀末から18世紀初頭にかけて、江戸近郊の千葉(野田・銚子など)で醤油製造が注目され、
「関東地廻り醤油=濃口醤油」が普及します。
これにより、天ぷら、蕎麦、蒲焼、握り寿司など、江戸グルメの発展を支えます。 - 濃口醤油の開発・普及の背景として、江戸の地下水や風土に適した製造法への適応、
また江戸の人口増加・物流の発達(水運の利用)があります。 - 製造工程としては、小麦や大豆を炒め、麹と塩を加えて大桶で発酵させ、熟成後に搾って醤油としました。
- 江戸後期には、醤油は素朴調味料から江戸庶民の味覚の中心的役割を担い、
寿司やそばつゆ「江戸の味」を象徴するような存在となりました。 - 醤油の輸出も江戸時代から始まり、鎖国下の出島を通じた「コンプラ瓶」と呼ばれる
磁器の容器でオランダなど欧州に輸出されていました。
江戸時代に濃口しょうゆが一般化したことで、今日まで続く和食の多くが完成し、
よくある質問と専門家の回答(FAQ)
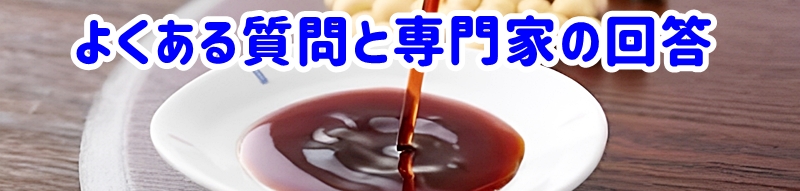
Q1. 醤油は調味料なのに、なぜタンパク質群なの?
A. 醤油は大豆が原料で、アミノ酸やタンパク質が含まれるため、6つの食品群や4つの食品群では「タンパク質群」に分類されます。
Q2. どの醤油を選べばいい?
A. 料理の目的や好みに合わせて選ぶのがコツ。刺身や照り焼きにはたまり醤油、煮物や炒め物には濃口や淡口、色を活かすなら白醤油がおすすめです。
Q3. 醤油の保存方法は?
A. 開封後は冷蔵庫保存が推奨。風味や品質を長持ちさせるコツです。
醤油は何群?まとめ表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 醤油の分類 | 6つの食品群:1群、4つの食品群:2群 |
| 主な栄養素 | アミノ酸、ビタミンB群、ミネラル |
| 種類 | 濃口、淡口、たまり、再仕込み、白醤油 |
| メリット | 旨味・抗酸化・保存性・健康効果 |
| デメリット | 塩分が多い、摂り過ぎ注意 |
| おすすめ用途 | 料理別に使い分けると美味しさUP |
| 保存方法 | 冷暗所、開封後は冷蔵庫 |
料理好き必見!プロが教える醤油との賢い付き合い方

醤油が6群であること、そしてその栄養的な特性を理解した上で、いよいよ実践編です。
ここでは、私が現場で培ってきた、減塩しながらも料理の満足度を上げるための具体的なテクニックをご紹介します。
テクニック①:香りを活かす「仕上げ醤油」で減塩でも満足
醤油の魅力の一つに、加熱した時の香ばしい「香り」があります。
この香りは、食欲をそそり、満足感を与えてくれます。
コツは、調理の最後に加えること。
例えば、野菜炒め。最初から醤油を入れて炒めると、塩分はしっかり付きますが、香りは飛んでしまいます。
そうではなく、ほぼ火が通った最後の段階で、鍋肌にジュワっと醤油を回しかけてみてください。
香ばしい香りが一気に立ち上り、少ない量の醤油でも味と香りが際立ち、満足感が格段にアップします。
これを私は「香りのコーティング」と呼んでいます。
テクニック②:出汁や酸味を組み合わせる「合わせ技」
醤油の量を減らすと、味がぼやけがちです。
そこでおすすめなのが、他の味覚をプラスすること。
- 出汁の旨味
昆布やかつお節でしっかり取った出汁をベースにすれば、醤油の量を半分にしても、出汁の旨味が味の土台を支えてくれるため、物足りなさを感じません。 - 酸味の活用
酢やレモン汁などの酸味を加えると、味覚が刺激され、塩味が引き立ちます。和え物やドレッシングを作る際に醤油を少し減らし、その分お酢を加えてみてください。さっぱりとしながらも、味が引き締まります。
テクニック③:醤油の種類を使い分けて風味をコントロール
先ほどの比較表で見たように、醤油には様々な種類があります。これを使い分けるのもプロの技です。
- 煮物
最初は濃口醤油でベースの味をつけ、仕上げに香り付けでたまり醤油を少量加えると、色とコクに深みが出ます。 - お吸い物
素材の色と風味を活かしたいなら、白醤油や薄口醤油が最適です。 - 刺身
脂の乗った魚には濃厚なたまり醤油、白身魚には旨味のある再仕込み醤油など、素材によって変えるだけで、いつものお刺身が料亭の味に近づきます。
私が実践している具体的な醤油活用レシピ例
- 豚の生姜焼き
醤油、みりん、酒に、すりおろした玉ねぎを加えるのがポイント。
玉ねぎの酵素が肉を柔らかくし、甘みと旨味もプラスされるので、醤油の量を2割ほど減らせます。 - きのこの炊き込みご飯
きのこを先に少量の醤油とみりんで炒めておきます。この「下味」がポイント。
炊き込む際の全体の醤油は控えめにしても、きのこ自体にしっかり味が付いているので、
香り高く満足感のある仕上がりになります。
醤油は「タンパク質群(1群/2群)」に分類され、健康・美味しさの両面で優れた調味料です。
料理好きなあなたも、今日から「醤油の種類」と「使い分け」を意識してみてください。
まずはご家庭の醤油を見直し、料理に合わせて使い分けてみましょう!
もし迷ったら、この記事をブックマークして何度でも参考にしてください。
醤油は何群?まとめ
- 醤油は6つの食品群で「1群」、4つの食品群で「2群」に分類される
- 原料の大豆由来でタンパク質やアミノ酸を含む
- 3色食品群では分類外(調味料扱い)
- JAS規格で5種類(濃口、淡口、たまり、再仕込み、白)
- 料理ごとに使い分けると美味しさがアップ
- アミノ酸やビタミンB群、ミネラルが含まれる
- 抗酸化作用や保存性も高い
- 減塩にはスプレーや小皿使いが効果的
- 塩分が多いので摂り過ぎに注意
- 丸大豆・本醸造の醤油は風味が良い
- 開封後は冷蔵庫保存が推奨
- 淡口醤油は色が薄いが塩分は高め
- たまり醤油は旨味が濃く刺身に最適
- 再仕込み醤油は高級料理向き
- 白醤油は素材の色を活かす料理に
- 料理教室でも使い分けの質問が多い
- 失敗談:淡口醤油の使いすぎに注意
- FAQでよくある疑問を解決
- この記事を参考に、醤油の知識を日々の料理に活かそう

コメント