
「今日のスープ、何かが足りない…」
「創味シャンタンと鶏がらスープの素、なんとなく使ってたけど、違いって何?」
こんにちは。以前都内で小さな中華料理店に勤めていた、料理人のケンジです。
修行時代、親方に「調味料の1グラムにこだわれ!」と、耳にタコができるほど言われ続けてきました。
実のところ、この創味シャンタンと鶏がらスープの素は似ているようで、
実は全くの別物なんです。
- 結論、違いは「うま味の複雑さ」
- 創味シャンタンは「万能中華調味料」
- 鶏がらスープは「シンプルなだしの素」
- 料理別の使い分けが味の決め手になる
- 代用はできるが注意点があることを知る
- コスパや成分の違いも詳しく解説します
【結論】創味シャンタンと鶏がらスープの最大の違いは「うま味の複雑さ」
早速、核心からお伝えします。
この二つの最大の違いは、うま味の「種類」と「複雑さ」にあります。
- 創味シャンタン
豚骨や鶏骨をベースに、香味野菜やスパイスを20種類以上ブレンドした「万能中華調味料」です。
これ一つで味がほぼ完成します。 - 鶏がらスープの素
鶏骨と鶏肉のうま味をギュッと凝縮した「だしの素」です。
味の土台を作る、シンプルな役割を担っています。
創味シャンタンと鶏がらスープの違い一覧表
| 項目 | 創味シャンタン(DX) | 鶏がらスープの素 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 万能中華調味料 | だしの素 |
| 主な原材料 | 豚骨、鶏骨、香味野菜、スパイス等 | 鶏骨、鶏肉、チキンエキス等 |
| 味の方向性 | 濃厚で複雑、こってり | あっさりでクリア、シンプル |
| 得意な料理 | チャーハン、中華スープ、八宝菜 | 中華粥、卵スープ、和え物 |
| 香りの強さ | 強い(香味野菜やスパイス) | 穏やか(鶏の香り) |
| 塩分の強さ | 比較的強い | やや控えめ |
| これだけで味が決まるか | ほぼ決まる | 決まらない(塩や醤油が必要) |
いかがでしょうか? 全くの別物であることが、お分かりいただけたかと思います。
それでは、それぞれの特徴をさらに深掘りしていきましょう。
創味シャンタンとは?
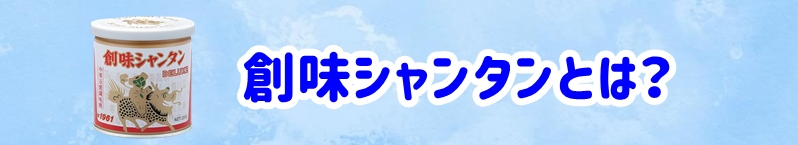
「シャンタン」とは、中国語で「上湯(シャンタン)」と書き、
最高級の中華スープを意味します。 まさに、その名の通りの調味料なのです。
原材料から見る創味シャンタンの特徴
創味シャンタンの原材料表示を見てみましょう。
食塩、動植物油脂(牛脂、豚脂、なたね油、ごま油)、砂糖、乳糖、小麦粉、香辛料…。
実に多くの材料が使われています。
注目すべきは、豚と鶏の両方が使われている点です。
豚のコクと、鶏のうま味。 そこに香味野菜やスパイスが加わることで、
家庭では再現が難しい、プロの「あの味」が生み出されているわけです。
どんな味?こってり濃厚なうま味
スプーンで少し舐めてみると、ガツンとくる塩味と、
複雑で濃厚なうま味が口の中に広がります。
これは、ラーメン屋さんのスープのような、力強い味わい。
少量でも、料理全体の味を支配するほどのパワーを持っています。
創味シャンタンが得意な料理【プロの使い分け術】
創味シャンタンは、その力強い味わいから、
味の輪郭をはっきりさせたい料理に最適です。
- チャーハン
お店のようなパラパラ感と香ばしい風味が出ます。 - 餃子の下味
肉だねに練り込むと、肉汁のうま味が格段にアップします。 - 唐揚げの下味
いつもの唐揚げが、本格中華の味わいに変わるでしょう。 - 野菜炒め
これ一つで味が決まるので、まさに時短の救世主です。
まさに「主役級」の調味料と言えるでしょう。
鶏がらスープの素とは?
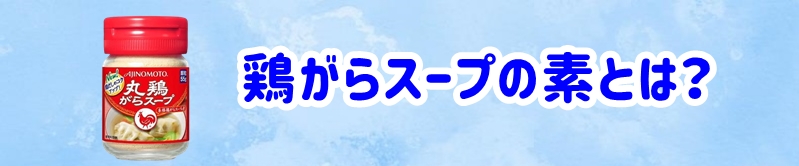
一方で、鶏がらスープの素はどうでしょうか。
こちらは、創味シャンタンとは対照的な魅力を持っています。
原材料から見る鶏がらスープの素の特徴
鶏がらスープの素の原材料は、非常にシンプルです。
チキンエキスパウダー、食塩、デキストリン、野菜エキスパウダーなど。
主役はあくまで「鶏」です。
豚や多くのスパイスは入っていません。
だからこそ、素材の味を邪魔しない、引き算の美学が光る調味料なのです。
どんな味?あっさりクリアなうま味
鶏がらスープの素は、口に含むと、優しくクリアな鶏のうま味がふんわりと広がります。
創味シャンタンのような強烈なインパクトはありません。
しかし、この「優しさ」こそが、鶏がらスープの素の真骨頂なのです。
鶏がらスープの素が得意な料理【基本の「き」】
鶏がらスープの素は、素材の味を活かしたい料理や、味の土台作りに欠かせません。
- 卵スープ
ふわふわ卵の優しい味わいを引き立てます。 - 中華粥
お米の甘みと鶏のうま味が見事に調和します。 - ナムル
ごま油と塩、そして鶏がらスープの素。これだけで絶品です。 - 和食のだし
実は、お吸い物や煮物の隠し味にも使えるんです。
こちらは、料理の名脇役といったところでしょうか。
【失敗談】私が創味シャンタンで大失敗した話
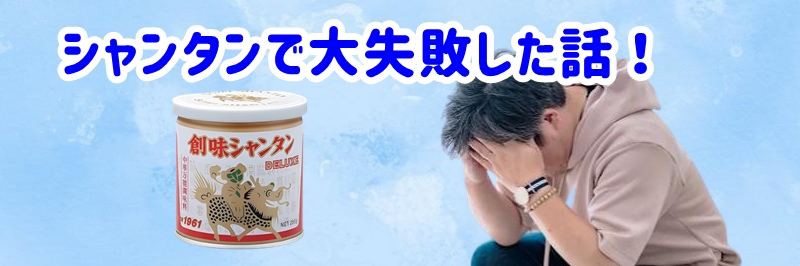
ここで少し、私の恥ずかしい失敗談をお話しさせてください。
まだ見習いだった20歳の頃、2005年の夏のことです。 賄いで中華丼を作ることになりました。
「親方の味を再現してやる!」と意気込んだ私は、
創味シャンタンをレシピの倍量、ドバっと入れてしまったのです。
「味が濃い方が、パンチがあって美味いはずだ」と。
結果は、惨憺たるものでした。 出来上がったのは、塩辛くて味が濃すぎる、
とても食べ物とは言えない代物。 野菜の甘みも、海鮮のうま味も、
全てが創味シャンタンの強い味に塗りつぶされていました。
親方には「バカヤロウ!調味料は魔法の粉じゃねぇ!素材との対話だ!」と、こっぴどく叱られました。
この失敗から得た教訓は、「創味シャンタンは少量から試し、全体のバランスを見ること」です。
主役級の力を持つからこそ、その使い方には細心の注意が必要なのです。
皆さんも、どうかお気をつけください。
創味シャンタンと鶏がらスープ、使い分け徹底ガイド
さて、それぞれの特徴が分かったところで、具体的な使い分けを見ていきましょう。
これができれば、あなたの料理は格段にレベルアップします。
【スープ】創味シャンタンで本格中華、鶏がらスープで優しい味
- 本格的なワンタンスープやラーメンスープを作りたいなら、迷わず創味シャンタンを。
濃厚なコクが、お店の味を再現してくれます。 - ふんわり卵の中華スープや、春雨スープなど、優しい味わいを求めるときは鶏がらスープの素で決まり。
素材の風味が活きます。
【炒め物】コク出しなら創味シャンタン、風味付けなら鶏がらスープ
- 豚肉とキクラゲの卵炒め(ムーシーロー)や、レバニラ炒めなど、
ご飯が進むガッツリ系の炒め物には創味シャンタンが最適です。 - 青菜の塩炒めなど、野菜そのものの味を楽しみたい時は、
鶏がらスープの素を少量加えるだけで、うま味の底上げができます。
【和食・洋食にも?】意外な使い方と注意点
実のところ、この二つは中華以外にも活躍します。
- 創味シャンタン
ポトフやカレーの隠し味に少量加えると、驚くほどコクが深まります。
ただし、入れすぎは禁物です。 - 鶏がらスープの素
炊き込みご飯やパスタのベース、フライドポテトのシーズニングにも。
汎用性の高さは抜群です。
【独自調査】コスパ最強はどっち?1杯あたりの価格を比較!
毎日使うものだから、コストパフォーマンスも気になりますよね。
そこで、2025年8月現在の近所のスーパーの価格を参考に、独自に調査してみました。
| 商品 | 内容量 | 実売価格(税込) | メーカー推奨使用量(スープ1杯) | 1杯あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 創味シャンタンDX | 250g | 648円 | 4g | 約10.4円 |
| ユウキ食品の鶏がらスープ | 130g | 378円 | 3g | 約8.7円 |
※価格は店舗により変動します。
調査の結果、1杯あたりのコストは鶏がらスープの素に軍配が上がりました。
とはいえ、創味シャンタンはそれだけで味が決まることを考えると、
他の調味料代が浮くとも言えます。
どちらがお得かは、作る料理によって変わってきそうですね。
【体験談】鶏がらスープの素で味が決まらない…その原因と解決策
「鶏がらスープの素を使っているのに、どうも味がぼやける…」
これも、料理教室の生徒さんからよく聞くお悩みです。
実は私も、独立したての頃、コストを抑えようと鶏がらスープの素をメインに使っていた時期がありました。
しかし、どうにも味が決まらない。
スープが「薄い水」のようになってしまうのです。
その原因は、「鶏がらスープの素は『だし』であり、
それ自体に強い塩味はない」という基本を忘れていたからでした。
創味シャンタンと同じ感覚で使っていたのです。
解決策は、至ってシンプル。
鶏がらスープの素でうま味の土台を作った後、必ず塩、こしょう、そして少量の醤油やごま油で味を調えること。
これを徹底するだけで、スープの輪郭がくっきりと浮かび上がります。
鶏がらスープの素は、あくまで味の「サポーター」であることを忘れないでください。
関連記事の解説
創味シャンタンとウェイパーの違いは?

これは本当によく聞かれる質問です。結論から言うと、中身はほぼ同じものと考えて良いでしょう。
もともと創味食品が廣記商行のブランド「味覇(ウェイパー)」を製造していましたが、
契約終了に伴い、創味食品が自社ブランドとして「創味シャンタン」を販売開始した経緯があります。
現在の味覇は別の会社が製造しており、レシピも少し違うようですが、基本的な使い方は同じです。
創味シャンタンは体に悪い?添加物について
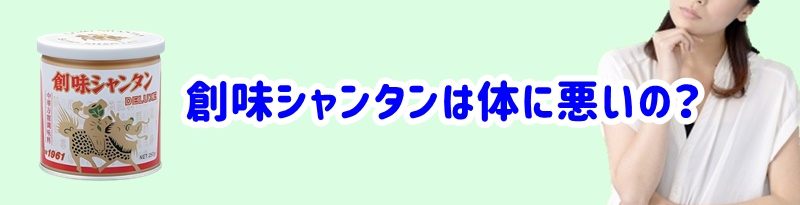
創味シャンタンには食塩、調味料(アミノ酸等)、動物油脂などが含まれており、
主に以下の点が気になる方がいます。
- 塩分が高い
小さじ1杯(約5g)で塩分は約2g程度含まれます。日本人の1日の塩分摂取目標量は男性7.5g未満、女性6.5g未満ですから、使いすぎると塩分過多になりやすいです。 - 化学調味料
グルタミン酸ナトリウムなどのうま味調味料が含まれています。これ自体は安全性が確認されている食品添加物ですが、気にする方もいます。 - 動物性油脂
チキンオイルなどが含まれており、カロリーや脂質が気になる場合もあります。
適切に使えば問題ない
ただし、創味シャンタンは「調味料」であり、適量を料理に使う分には特に問題ありません。
大切なのは
- 使用量を守る(入れすぎない)
- 他の料理の塩分とのバランスを考える
- 毎日大量に使い続けるのは避ける
塩や醤油、味噌なども使いすぎれば健康に良くありませんが、適量なら問題ないのと同じです。
「体に悪い」というより「塩分が高めなので使用量に注意が必要」というのが正確な理解だと思います。
塩分が気になる場合は、使用量を減らしたり、他の調味料と組み合わせて使うなど工夫するとよいでしょう。
創味シャンタンの代用は鶏がらスープでできる?
答えは「条件付きでYES」です。
創味シャンタンがない場合、鶏がらスープの素で代用は可能です。
ただし、鶏がらスープの素だけでは、あの濃厚なコクは出ません。
代用する際は、鶏がらスープの素に、おろしにんにく・しょうが、ごま油、
そしてほんの少しのオイスターソースや醤油を加えてみてください。
そうすることで、創味シャンタンの風味に近づけることができます。
Q&A|創味シャンタンと鶏がらスープのよくある質問
Q1. 開封後の保存方法はどうすればいいですか?
A1. 創味シャンタン(缶タイプ)も鶏がらスープの素(顆粒タイプ)も、冷蔵庫での保存が基本です。
特に創味シャンタンは油脂分が多いので、常温だと劣化しやすくなります。
清潔なスプーンを使い、開封後はなるべく早く使い切りましょう。
Q2. 塩分が気になります。どちらが塩分控えめですか?
A2. 商品によって異なりますが、一般的には鶏がらスープの素の方が塩分濃度を調整しやすいと言えます。
創味シャンタンは単体で味が濃いため、塩分を控えたい場合は使用量をかなり減らす必要があります。
栄養成分表示をしっかり確認しましょう。
Q3. チューブタイプと缶タイプ、中身は同じですか?
A3. はい、創味シャンタンのチューブタイプと缶タイプの中身は基本的に同じです。
チューブタイプはスプーンを使わずに済むので、衛生的で使いやすいのがメリットですね。
ご家庭での使いやすさに合わせて選ぶと良いでしょう。
創味シャンタンと鶏がらスープの違い!まとめ
最後に、この記事の要点を箇条書きでまとめます。
あなたのキッチンでの迷いが、今日でなくなれば幸いです。
- 創味シャンタンと鶏がらスープの違いは「うま味の複雑さ」です。
- 創味シャンタンは豚や野菜も入った「万能中華調味料」。
- 鶏がらスープの素は鶏特化の「シンプルなだしの素」です。
- 創味シャンタンは、これ一つで味がほぼ完成します。
- 鶏がらスープの素は、味の土台を作る役割を担います。
- チャーハンなど味を濃くしたいなら創味シャンタンがおすすめです。
- 卵スープなど素材を活かすなら鶏がらスープの素が良いでしょう。
- 創味シャンタンは主役級の調味料と言えます。
- 鶏がらスープの素は名脇役のような存在です。
- 失敗談として、創味シャンタンの入れすぎは味が濃くなりすぎます。
- 鶏がらスープの素で味が決まらないのは塩分不足が原因かもしれません。
- 代用は可能ですが、風味を近づける工夫が必要です。
- 鶏がらスープの素に香味野菜などを足すとシャンタンに近くなります。
- コストパフォーマンスでは、1杯あたり鶏がらスープの素が安い傾向にあります。
- ウェイパーと創味シャンタンは、もともとは同じ会社が作っていました。
- 添加物が気になる場合は、使用量を守ることが大切です。
- 開封後はどちらも冷蔵庫で保存するのが基本です。
- 塩分調整のしやすさでは鶏がらスープの素に分があります。
- それぞれの特徴を理解し、料理によって使い分けることが重要です。
- この知識が、あなたの料理をさらに美味しくするでしょう。
あなたの食卓が、もっと豊かで楽しいものになりますように。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。


コメント