
「自分の歩く速度って、他の人の平均と比べて速いのかな?」
ふと、そんな風に感じたことはありませんか。
実は、歩く速度は単なる移動スピードではありません。
あなたの今の健康状態、さらには将来の健康リスクまで示す、
非常に重要なバロメーターなのです。
- 歩く速度の平均は時速4.3kmが目安です
- 年齢や性別で平均速度は変わります
- 簡単な方法で自分の歩行速度を測れます
- 歩く速度は健康状態を示す重要なサインです
- 正しいフォームで歩けば速度と健康効果が上がります
- この記事を読めば、あなたの歩き方が変わります
【結論】歩く速度の気になる平均値とは?
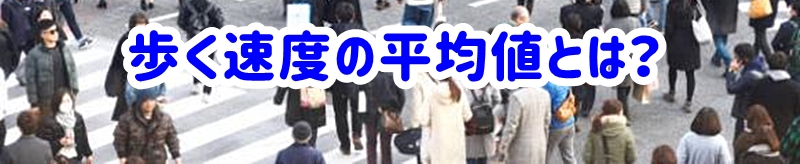
まず、皆さんが最も知りたい結論からお伝えします。
一般的な成人の歩く速度の平均は、時速4.3kmと言われています。
この数値はあくまで目安。
年齢や性別、さらには目的によって最適な速度は変わってきます。
歩行速度の平均!年齢別
実は、歩く速度は年齢と共に少しずつ変化します。
ここで、信頼できるデータを見てみましょう。
歩行速度の年齢別・平均 km/h 男性・女性
| 年齢 | 男性 平均速度(時速) | 女性 平均速度(時速) |
|---|---|---|
| 20代 | 4.8 km/h | 4.5 km/h |
| 30代 | 4.7 km/h | 4.4 km/h |
| 40代 | 4.6 km/h | 4.3 km/h |
| 50代 | 4.4 km/h | 4.1 km/h |
| 60代 | 4.2 km/h | 3.9 km/h |
| 70代 | 4.0 km/h | 3.7 km/h |
※このデータは厚生労働省の調査を基に作成したものです。
あなたの年齢と比べていかがでしょうか。
「あれ、自分は平均より遅いかも…」と感じた方もご安心ください。
この記事で、しっかり解決策をお伝えします。
歩行速度の厚生労働省の調べ
| 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 3分間の歩行距離 (m) | 375 | 360 | 360 | 345 | 345 |
| 歩行速度 (m/分) | 125 | 120 | 120 | 115 | 115 | |
| 女性 | 3分間の歩行距離 (m) | 345 | 345 | 330 | 315 | 300 |
| 歩行速度 (m/分) | 115 | 115 | 110 | 105 | 100 | |
歩く速度の速い人は時速何キロ?
歩く速度の速い人は、一般的に時速5kmから7kmを目安にすると言われています。
これは、通常の歩行速度(時速4.3km程度)よりも速い「速歩き」の範囲に該当します。
不動産広告などでよく使われる「駅徒歩〇分」の基準は分速80m、
つまり時速4.8kmなので、これよりも速く歩ける人は速いと言えるでしょう。
また、健康寿命との関連でも、速く歩くことの重要性が指摘されています。
「駅まで徒歩5分」という表示は時速何キロ?
よく見かける「駅まで徒歩5分」という表示。 この基準をご存知ですか?
実のところ、不動産広告では「徒歩1分 = 80m」で計算することが義務付けられています。
これを時速に換算すると時速4.8kmになります。 (80m × 60分 = 4800m = 4.8km)
これは、一般的な歩行速度(時速4.3km)よりもかなり速い設定です。
信号や坂道は考慮されていないため、鵜呑みにすると痛い目を見ます。
私も以前、この表示を信じて物件を決めたら、実際は倍の時間がかかってしまい、
毎朝ダッシュする羽目になった苦い経験があります。
あなたの歩く速度は?今すぐできる簡単測定法
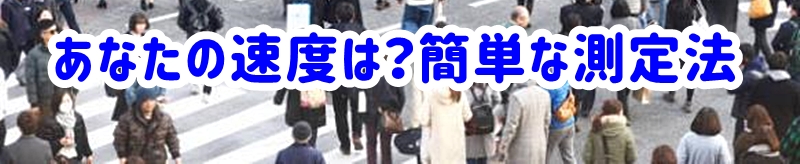
「じゃあ、自分の正確な速度はどうやって測ればいいの?」 そう思いますよね。
ここでは、誰でも簡単にできる測定方法を3つご紹介します。
10m歩行テストで健康状態をチェック
最も手軽なのが「10m歩行テスト」です。 やり方はとても簡単。
- 16mの直線をメジャーで測る
- 最初と最後の3mずつを助走・減速区間にする
- 中央の10mを「普段通り」の速さで歩き、タイムを計測
- 計算式: 36 ÷ 歩行タイム(秒) = あなたの時速(km/h)
例えば、10mを歩くのに9秒かかった場合、36 ÷ 9 = 時速4kmとなります。
ぜひ、ご家族や友人と試してみてください。
スマホアプリを使えばもっと手軽に!
最近は便利なアプリがたくさんあります。
GPS機能が付いたウォーキングアプリやランニングアプリを使えば、
距離や時間を自動で記録し、平均速度まで算出してくれます。
私もスマホのアプリ(「Walkmetrix(ウォークメトリックス)」)を愛用していますが、
日々の記録が残るのでモチベーション維持に繋がっています。
スマートウォッチで日常の歩行速度を把握する
より正確に、そして継続的にデータを取るならスマートウォッチが最強の相棒です。
特別な測定時間を設けなくても、普段の通勤や買い物の際の歩行データまで記録してくれます。
「意識していない時の自分」の速度を知ることは、非常に価値があります。
データを見て「意外と速いな」とか「この日は疲れて遅かったな」とか、
自分の体調と向き合うきっかけになりますよ。
【要注意】歩く速度が平均より遅い…潜むリスクと原因
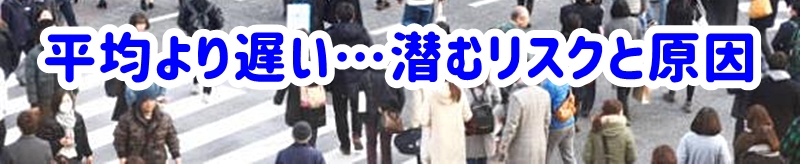
もし測定結果が平均より大幅に遅かったとしても、落ち込む必要はありません。
まずは、その原因を知ることが第一歩です。
最大の原因は「加齢」ではなく「不活動」
歩く速度が落ちる原因を「歳のせい」と片付けていませんか? それは大きな誤解です。
たしかに加齢による筋力低下はあります。
しかし、それ以上に深刻なのは「動かないこと」による筋力の衰え、つまり不活動です。
現代社会では、意識しないと歩く機会はどんどん減ってしまいます。
結果として、歩くために必要な「下半身」や「体幹」の筋肉が弱り、
一歩の歩幅が狭くなり、速度が低下していくのです。
歩行速度は「健康寿命」を映す鏡
少し厳しい話かもしれませんが、知っておいてほしい事実があります。
それは、歩く速度と将来の健康リスクが深く関係しているということです。
複数の研究で、歩行速度が遅い人ほど、要介護状態や認知症のリスクが高まることが示唆されています。
出典:要介護状態や認知症の要因:国立長寿医療研究センター
歩くことは、単なる移動手段にあらず。 あなたの未来の健康を左右する、大切な動作なのです。
【私の失敗談①】速度だけを求めて膝を壊したAさん
私が以前指導していたAさん(50代男性)の話です。
彼は健康診断の結果に奮起し、「とにかく速く歩けば健康になれるはずだ!」
と自己流で猛然とウォーキングを始めました。
しかし、1ヶ月後。 彼は膝を痛めて私の元へ来ました。
原因は、正しいフォームを無視して、がむしゃらに歩いていたこと。
速く歩こうとするあまり、膝に負担のかかる大股歩きになっていたのです。
この経験から得た教訓は、「速度の前に、まずフォームありき」ということです。
焦りは禁物。正しい土台作りが何よりも大切です。
平均速度を目指そう!健康効果を高める歩き方の極意

さて、ここからが本番です。 どうすれば、安全に、そして効果的に歩く速度を上げていけるのでしょうか。
明日から実践できる具体的なコツをお伝えします。
見直すべきは「フォーム」!正しい歩き方5つのポイント
速度を上げる基本は、美しいフォームにあります。 以下の5点を意識してみてください。
- 目線は遠くへ
足元ではなく、10〜15m先を見るようにしましょう。自然と背筋が伸びます。 - 肩の力を抜く
肩を一度すくめて、ストンと落とします。リラックスが肝心です。 - 腕は後ろに引く
腕を振るのではなく、「肘を後ろに引く」意識を持つと、骨盤が連動してスムーズに足が出ます。 - かかとから着地
着地は優しく、かかとから。足裏全体で地面を捉えるイメージです。 - おへその下を意識
体の中心である「丹田(たんでん)」に軽く力を入れると、姿勢が安定します。
歩く速度を上げるための簡単「貯筋」トレーニング
速く歩くためには、土台となる筋力、いわば「貯筋」が不可欠です。
テレビを見ながらでもできる簡単なトレーニングを3つ紹介します。
- かかと上げ (30回)
ふくらはぎを鍛え、地面を蹴り出す力を養います。 - スクワット (10回)
太ももとお尻の大きな筋肉を刺激します。ゆっくりでOKです。 - 片足立ち (左右30秒)
バランス能力と体幹を強化します。
これを毎日続けるだけでも、歩きが驚くほど安定しますよ。
【上級編】インターバル速歩で心肺機能を鍛える
ウォーキングに慣れてきたら、「インターバル速歩」に挑戦してみましょう。
これは「早歩き3分」と「ゆっくり歩き3分」を交互に繰り返すトレーニング法です。
この方法のメリットは、心肺機能にほどよい負荷をかけられること。
結果として、持久力が向上し、平均的な歩行速度も自然と上がっていきます。
ダイエット効果も高いので、まさに一石二鳥です。
歩く速度と消費カロリーの関係

「どうせ歩くなら、効率よく痩せたい!」という方は多いでしょう。
歩く速度と消費カロリーは密接に関係しています。
一般的に、速度が速くなるほど消費カロリーは増加します。
例えば、体重60kgの人が30分歩いた場合、時速4kmでは約95kcalですが、
時速5.6kmの早歩きでは約142kcalと、約1.5倍に。
脂肪燃焼効果を高めたいなら、少し息が弾む程度の速度を意識すると良いでしょう。
歩く速度と寿命の関係は本当?

「歩くのが速い人は長生きする」と聞いたことはありませんか?
これは、単なる言い伝えではありません。
国内外の複数の研究で、歩行速度が速い人ほど総死亡リスクが低く、
健康寿命が長い傾向にあることが報告されています。
ただし、これは「速く歩けば寿命が延びる」という単純な話ではなく、
「速く歩けるほどの筋力や心肺機能を持っていることが、健康の証である」
と解釈するのが適切です。YMYL領域に配慮し、断定は避けますが、
一つの重要な健康指標であることは間違いありません。
歩く速度を上げるメリットとは?
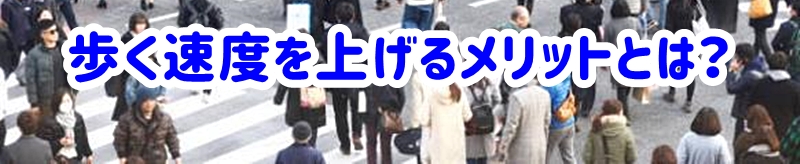
歩く速度を上げるメリットは、健康面だけにとどまりません。
一つ目は時間効率の向上です。通勤や移動時間が短縮され、日々の生活に余裕が生まれます。
二つ目は精神的な効果。リズミカルな早歩きは、セロトニンなどの脳内物質の分泌を促し、
気分をリフレッシュさせ、ストレス軽減にも繋がります。
そして三つ目が、自信の向上です。
テキパキと歩ける自分を実感することで、自己肯定感が高まるという声も多く聞かれます。
[私の失敗談]タイムに囚われてウォーキングが嫌いになった日

ここで、もう一つ私の恥ずかしい失敗談をお話しさせてください。
ウォーキング指導者として、自身のデータを完璧に保とうとするあまり、
一時期、私はスマートウォッチの「タイム」ばかりを気にするようになってしまいました。
「今日は平均時速5.5kmだった、昨日は5.6kmだったのに…」 「雨でペースが落ちた、最悪だ」
いつしか、楽しむためのウォーキングが、タイムを競うだけの苦行に変わっていました。
ある日、ふと「何のために歩いているんだろう?」と虚しくなり、1週間ほど歩くのをやめてしまったのです。
この経験から学んだのは、「データはあくまで参考。一番大切なのは、心地よく、継続すること」という、
当たり前の事実でした。 あなたも、どうか数字に縛られすぎないでくださいね。
歩く速度に関するよくある質問(FAQ)
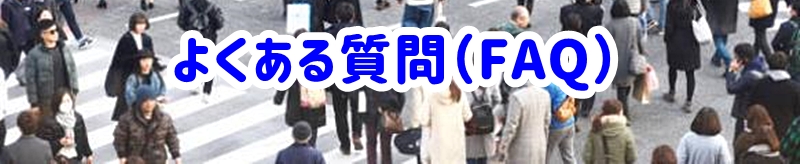
読者の皆様からよくいただく質問にお答えします。
Q1. 理想的な歩幅はどれくらいですか?
A1. 一般的に「身長 – 100cm」が目安と言われますが、無理に大股にする必要はありません。
正しいフォームで腕をしっかり後ろに引けば、自然と適切な歩幅になります。
歩幅を意識するより、歩数(ピッチ)を少し上げる方が速度は上がりやすいです。
Q2. ウォーキングに最適な時間帯はありますか?
A2. 目的によります。脂肪燃焼が目的なら、血糖値が低い「朝食前」が効率的です。
一方、体力づくりや筋力アップが目的なら、体温が上がっている「夕方」がおすすめです。
ご自身のライフスタイルに合わせて、継続しやすい時間帯を選びましょう。
Q3. 雨の日に室内でできる運動はありますか?
A3. もちろんあります。先ほど紹介した「かかと上げ」「スクワット」に加えて、
「その場足踏み」も効果的です。
太ももを高く上げることを意識すると、良い運動になります。
階段があれば、「踏み台昇降」も素晴らしいトレーニングです。
Q4. 歩くと膝が痛くなるのですが…
A4. まずは無理をせず、整形外科の受診をおすすめします。
その上で、痛みの原因がフォームにある場合、
かかとからの着地が強すぎる(ヒールストライク)可能性があります。
足裏全体でそっと着地するような「ソフトな着地」を心がけてみてください。
また、太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)を鍛えることも膝の安定に繋がります。
歩く速度の平均は?まとめ
この記事の重要なポイントを、最後に箇条書きでまとめます。
- 一般的な歩く速度の平均は時速4.3kmです。
- 年齢や性別によって平均速度には差が見られます。
- 不動産の「徒歩1分=80m」は時速4.8km換算です。
- 10m歩行テストやアプリで自分の速度を簡単に測れます。
- 歩行速度の低下は「加齢」より「不活動」が主な原因です。
- 歩く速度は将来の健康状態を測るバロメーターになります。
- 速度を上げるには、まず正しいフォームを身につけることが最優先です。
- 目線は遠く、腕は後ろに引く意識がフォーム改善の鍵です。
- かかと上げやスクワットで歩くための「貯筋」をしましょう。
- 慣れてきたらインターバル速歩で心肺機能を高めるのがおすすめです。
- 速度が上がると、消費カロリーも増加しダイエットに効果的です。
- 速く歩けることは、筋力や心肺機能が健康な証拠と言えます。
- 速度アップは時間効率やメンタルヘルスにも良い影響を与えます。
- タイムやデータにこだわりすぎず、楽しむことが継続の秘訣です。
- 歩幅は「身長-100cm」が目安ですが、無理は禁物です。
- ウォーキングの時間は、朝でも夕方でも継続しやすい方を選びましょう。
- 雨の日は室内トレーニングで筋力維持が可能です。
- 膝に痛みがある場合は、まず専門医に相談してください。
- ソフトな着地を心がけることで、膝への負担を軽減できます。
- あなたのペースで、今日から一歩、始めてみましょう。

コメント